お墓の多様化
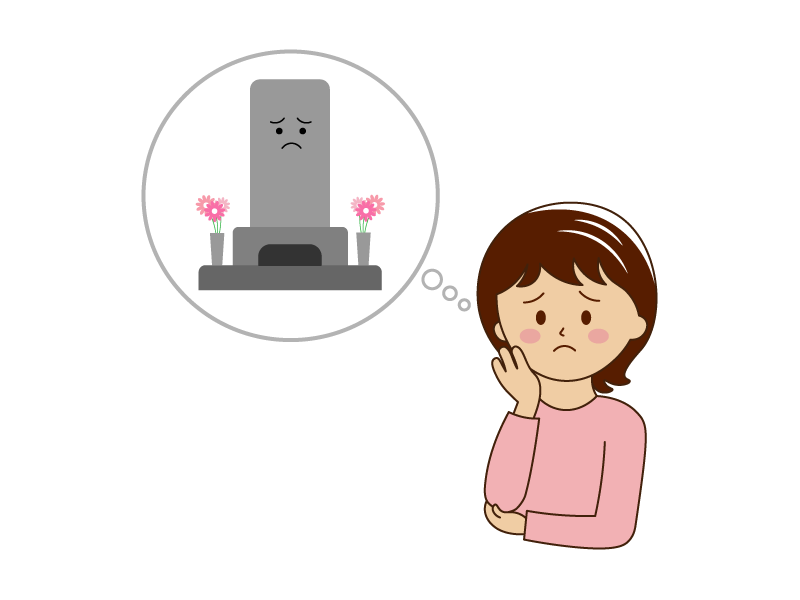
文武天皇4年旧暦3月10日(700年4月3日)に 法相宗の僧・道昭が火葬され、記録上はこれが日本初の火葬とされています。現代日本では火葬が当たり前になっていますが、世界の多くは宗教上の理由から土葬が中心です。
お墓や埋葬については、埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号))によって決められています。埋葬・火葬・改葬についての概略は「(第3条〜第9条)埋葬や火葬は死亡後24時間を経過してからでなければならない(第3条)。納骨は、都道府県知事の許可を受けた「墓地」以外でしてはならない(第4条)。埋葬、改葬、火葬には市町村長の許可が必要で、埋葬許可証、改葬許可証、火葬許可証を交付しなければならない(第5条・第8条)。身寄りのない人の火葬や埋葬は、死亡地の市町村長が「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」に基づいて行う(第9条)。」とあり、火葬は義務ではありません。だから、最近のような散骨などが法的な問題がないわけです。お墓も石造りである義務はないので、樹木葬なども普及しているわけです。かといって、昔のように自宅の敷地に墓を作ることはなかなかできなくなりました。墓地としての許可は一般的にお寺や神社のような宗教施設に限定されています。実際に個人墓地を作ることは法律上は可能ですが、かなり面倒な手続きが必要なので、まず個人は諦めます。(https://shiromaraku.jimdofree.com/墓地等経営許可申請を参照)しかし遺骨を自宅で保管することはできます。「厚生労働省の「墓地、埋葬等に関する法律」によれば、故人の遺骨を自宅に保管することは違法ではないと規定されています。しかしながら、仏教においては四十九日が過ぎた後、通常は故人の遺骨をお墓に納めます。そのため、自宅で遺骨を保管することが違法だと勘違いされることもあるかもしれません。
近年では、お墓に対する考え方が多様化しています。お墓を建てない理由や、遺骨をお墓に納めずに手元で供養したいという思いをお持ちの場合には、自宅での保管に問題はありません。」(https://www.yumemidou.jp/column/125/)遺体を放置するのは犯罪ですが、火葬した焼骨を埋葬せずに保管してもよいのです。その上で仏として供養することを「手元供養」といいます。骨壺などの容器に入れて、仏壇などに安置するなどの敬意を払う必要があります。よく位牌などを置きますが、位牌はお墓の代理なので、実際の遺骨を安置してもよいわけです。故人が家族と共に心穏やかに過ごせる環境を整えるわけです。形見を大切にするのと同じ感覚です。また一部を海や山に返すことは可能ですが、その場合、勝手にできるわけではなく、その海や山を管理する人や地域の許可が必要です。遺骨をお墓に埋葬するのは仏教の習慣であり、檀家で家の宗教がある場合は旦那寺の墓地に埋葬するのが普通ですが、最近のように宗教の信者でない人は高い墓地を借りるのも負担なので、安い樹木葬にしたり、散骨したり、手元供養にする人が増えるのは当然の社会現象です。これは庶民の側に問題があるのではなく、宗教の側に問題があると考えるべき社会現象です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |


