立夏
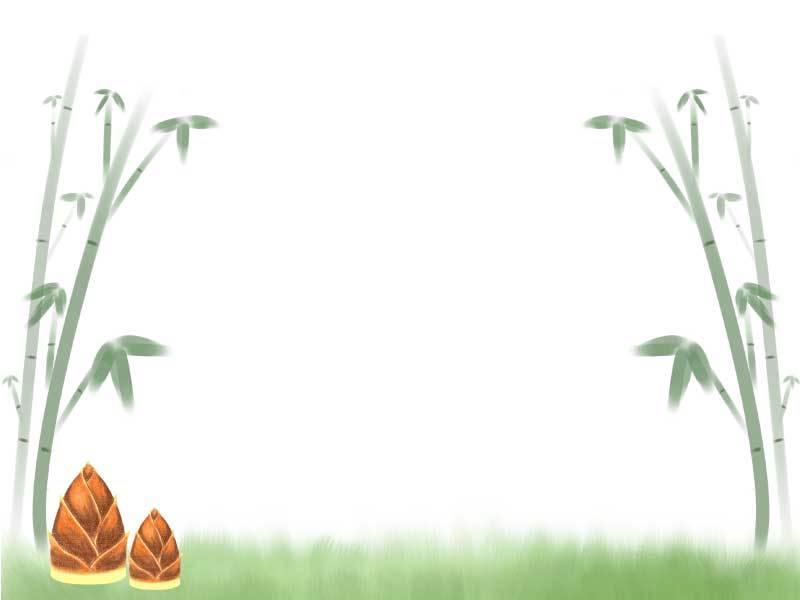
立夏(りっか)は二十四節気の一つで、春分と夏至の中間に位置し、暦の上で夏の始まりを示します。2025年の立夏は5月5日から始まり、次の節気である小満までの約15日間を指します。立夏は「夏の気配が立ち上がる」という意味を持ち、山々の緑が濃くなり、爽やかな風が吹き始める時期です。この時期はゴールデンウィークとも重なり、自然を楽しむのに最適な季節です。
立夏の時期には端午の節句が含まれるため、柏餅や粽(ちまき)を食べる風習があります。柏餅は家系の繁栄を象徴し、粽は邪気を払う意味を持つと言われています。立夏の頃に見られる代表的な花には藤(ふじ): 薄紫色の房状の花が美しく、棚に沿って咲く様子は見事です。藤で有名な観光地も増えてきました。躑躅(つつじ)は公道や草原で見られる花で、各地でつつじ祭りが開催されます。漢字がなかなかむずかしいですね。石楠花(しゃくなげ)は 鞠のような形の花が特徴で、葉には毒があるため鹿に食べられません。立夏の時期に旬を迎える食べ物には以下があります。筍(たけのこ)雨後の筍という言葉があるほど、この時期に多く採れます。竹カンムリに旬という漢字も象徴的です。そして初鰹:です。江戸時代から人気の魚で、この時期のさっぱりとした味わいが特徴です。「目に青葉、山ほととぎす、初鰹」という句は有名です。また、この時期には柏餅と粽(ちまき)が和菓子屋の店先に並びます。端午の節句に欠かせない和菓子です。
立夏は次の七十二候に分けられます:
初候: 蛙始鳴(かわずはじめてなく)
冬眠から目覚めた蛙が鳴き始める時期です。田舎暮らしでないと、なかなかこういう風情には出会えないものですが、旅行先で少し気を配ると聞くことができます。蛙の鳴き声に関する童謡も多いので、思い出して歌ってみてはいかがでしょうか。
次候: 蚯蚓出(みみずいづる)
冬眠していたミミズが地上に出てくる時期です。ミミズというと気味悪がる人が多くなりましたが、昔は土壌が豊かな印として重宝したものです。
末候: 竹笋生(たけのこしょうず)
タケノコが地中から顔を出す時期です。近年は竹林も荒れてきて、タケノコ農園でタケノコ掘りをするのが一般的になってきました。竹林も昔は平地に多くあり、風情のある風景でしたが、今では平地の竹林は伐採され、ほとんどが山地にあります。そのためタケノコ掘りも苦労するそうです。また放置された竹林のタケノコは味も悪く、きれいな竹林を保つには、枯れた竹の除去や地面の土壌改良など、多くの苦労があります。昔は竹は重要な資材で、生垣のような大きなものから、竹かごに至るまで、用途も広かったのですが、現代はプラスチックに代わってしまいました。竹は焼いて竹炭としても利用できますし、プラスチックが問題になっている現在、竹の利用を復興することが、環境にもよく、美しい日本の原風景を取り戻す象徴になると思われます。そういう運動が環境保護団体からもほとんどなく、政策としてもでてこないのは残念なことです。
立夏は自然の変化と恵みを感じるのにぴったりの季節です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


