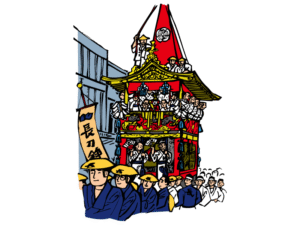七夕と小暑

7月7日といえば七夕です。織姫と彦星が年に一度、天の川を渡って出会うというロマンチックな物語とともに、短冊に願いごとを書いて笹に飾る風習が広く親しまれています。しかし、漢字では「七夕」と書くのに、なぜ「しちせき」ではなく「たなばた」と読むのでしょうか。
この不思議な読み方の背景には、日本と中国の文化が交差し融合した歴史があります。「七夕」はもともと中国から伝わった行事で、牽牛(けんぎゅう)と織女(しょくじょ)の星が年に一度出会うという伝説に基づいた「七夕節」が起源です。中国ではこの日を「七夕(チーシー)」と呼び、日本では当初「しちせき」と音読みされていました。奈良時代から平安時代にかけては、宮中で詩歌を詠み、星に願いを託す行事として定着していきました。一方で、日本には古くから「棚機(たなばた)」という神事が存在していました。「棚機津女(たなばたつめ)」と呼ばれる女性が、水辺の小屋に籠もり、神に捧げるための布を機織りする禊(みそぎ)の行事です。この風習は『万葉集』などにも記されており、豊穣や災厄除けを祈願する重要な儀式として古代の人々に親しまれていました。やがて、中国から伝わった「七夕」と、日本固有の「棚機」の信仰が結びつき、読み方として「たなばた」が七夕の字に当てられるようになりました。平安時代以降には、宮中だけでなく民間でもこの行事が浸透し、「七夕(たなばた)」として広く知られるようになっていきます。「たなばた」という読み方は、中国の星祭りと日本の禊儀礼という異なる文化が重なり合うことで生まれた、いわば言葉と行事の“習合”なのです。
暦の上で夏をあらわす言葉のひとつに「小暑(しょうしょ)」があります。二十四節気のひとつで、例年7月7日頃にあたります。この日を境に、季節は梅雨から本格的な夏へと移り変わっていきます。文字どおり「暑さが少しずつ本格化し始める」時期という意味で、同時に「大暑(たいしょ)」へと続く夏の階段の第一歩でもあります。例年だと小暑の頃、日本列島はまだ梅雨明け前で湿気の多い日々が続きますが、日差しには次第に力強さが増し、空の青さにも夏の気配が感じられます。蝉の初鳴きが聞こえはじめたり、七夕の行事が行われたりと、自然と文化が重なる美しい時期でもあります。この時期の七十二候では、「温風至(あつかぜいたる)」(初候)「蓮始開(はすはじめてひらく)」(次候)「鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)」(末候)と続きます。あたたかい風が吹きはじめ、蓮の花が水面に顔を出し、鷹の子が飛ぶことを覚えるという夏の命の躍動を感じさせる情景です。また、小暑から数えて11日目頃には「土用入り」が訪れ、これは季節の土用(四季の変わり目)のひとつで、特に夏の土用は体調を崩しやすいとされています。そのため昔から「土用の丑の日」に鰻を食べる習慣が根付いてきました。暑さを乗り切るための知恵と工夫が、この時期の暮らしには随所に息づいているのです。小暑は、ただ暑さの始まりを告げるだけでなく、自然と人の生活が調和してきた時間の入り口でもあります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |