海を思う、景色を尊ぶ─記念日が語る日本のこころ
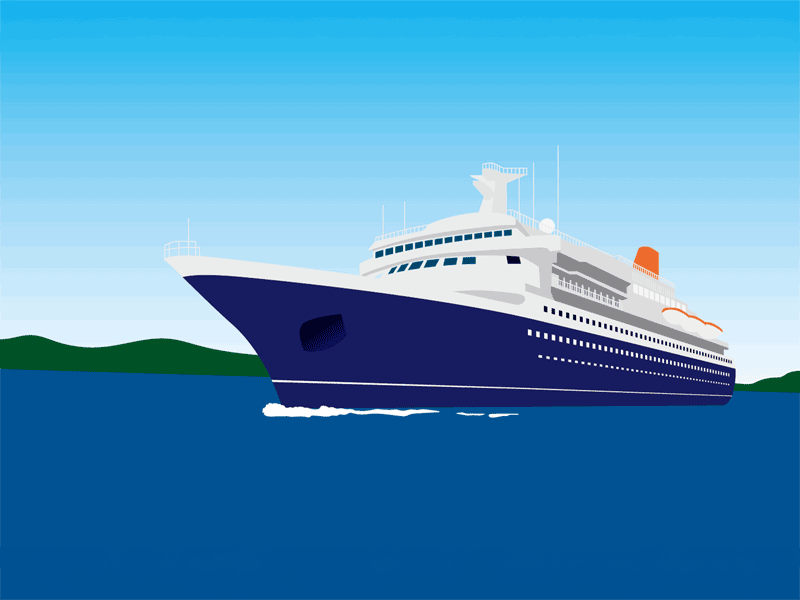
7月の連休に差しかかるころ、私たちは「海の日」や「日本三景の日」といった記念日に出会います。これらは一見、祝日や観光の日として受け止められがちですが、その背景には、自然との共生、美への敬意、そして歴史へのまなざしが隠されています。それぞれの記念日を通して、私たちが何を大切にしてきたのか、今いちど振り返ってみましょう。
「海の日」は、現在では7月第3月曜日に定められている国民の祝日で、日本の国民祝日の中でも比較的新しい部類に入ります。制定は1995年、施行は1996年と、平成期に生まれた祝日ですが、その起源は明治時代にまでさかのぼります。元々は「海の記念日」として、明治天皇が明治9年に東北地方巡幸の帰路、灯台船「明治丸」で無事に横浜港へ帰着した日(7月20日)を記念したものでした。日本が近代国家として自国の海洋交通や海軍力を整備していく中、「海の恩恵への感謝と海洋国家としての自覚」が芽生えた象徴の日でありました。現在の「海の日」もその理念を引き継ぎ、国土の多くを海に囲まれ、海運・漁業・観光に依存する日本にとって、「海を通じて得られる恩恵」に改めて思いを馳せる日として位置づけられています。この日には、多くの港町で灯台や船舶、海の安全祈願に関する式典が行われるほか、海にまつわる地域イベントやマリンスポーツ体験も盛んになります。特に子どもたちにとっては、自然とのふれあいの機会にもなっており、「海を学ぶ日」としても機能しているのです。
また「日本三景の日」でもあります。江戸時代の儒学者・林春斎が『日本国事跡考』の中で讃えた三つの風景、「松島(宮城)」「天橋立(京都)」「宮島(広島)」を記念したもので、制定日は7月21日。林春斎の誕生日にちなんでいます。これら三景は、いずれも海と関わりの深い景勝地です。海がつくり出す自然の造形と、それに寄り添う人々の営みが調和することで、芸術的ともいえる風景が形成されました。海岸線に浮かぶ松島の小島群、天橋立の砂洲、厳島神社の鳥居が海に立つ様子──これらはすべて、「海」が生み出した造形美であると言えるでしょう。「日本三景の日」は観光振興という側面もありますが、それ以上に、「景観を尊ぶ」という日本人の美的感覚を再確認する機会にもなっています。単に「観光地を訪れる」のではなく、「そこにある自然と文化の調和」に思いを巡らせることが、この記念日の本質的な意義なのです。
「海の日」も「日本三景の日」も、どちらも「海」という大自然と深く関わっています。そして、共通しているのは、「自然の恩恵に感謝し、共に生きる姿勢を忘れないこと」、そして「その美しさや力を称える心」を育むことにあります。
海は、命の源でもあり、時に人命を脅かす荒れた存在でもあります。風光明媚な景観も、気象や地形、歴史といった複数の要素が絡み合って形成された奇跡的な産物です。私たちの祖先は、そうした自然の営みに敬意を払いながら、生活の知恵や文化を築いてきました。感謝したいですね。

