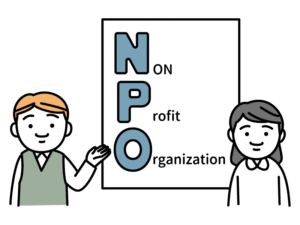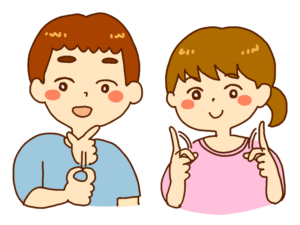手話技能検定の理念と言語技能

手話技能検定協会の設立時と現在では24年の経過があり、その間に政府の制度はめまぐるしく変わりました。しかし当協会では今も設立以来の理念を守っており、基本技法は変わりません。理念とは、「手話は言語である」という前提で、英語検定や日本語検定があるように、言語としての検定試験が可能である、という思想です。今では「手話が言語である」ことは当たり前のように思われていますが、設立当時は反対意見の人々が多く、「手話は聾者とのコミュニケーションのツールだ」という主張が強くありました。コミュニケーションのツール、ということは、それは言語ではないのか、という疑問がありますが、なぜか「ツールであって、言語ではない」という主張が目立ちました。確かにコミュニケーションのツールには、言語以外の要素つまり非言語情報が多くあります。身振りや表情は非言語情報なので、それらを多く使う手話は非言語情報だ、ということだったのかもしれません。しかしそういう、はっきりした反論はほとんどなく、根底には聴者が手話に関する事業をすることへの感情的反発があったようです。「手話を金儲けにするな」「手話は聾者のものだから、聾者の許可なく事業をするな」という意見は今も散見されます。その典型例が「手話はろう者の言語である」という定義です。この排他的定義は、「聴者は手話をしてはいけない」ようなニュアンスがあり、それは手話通訳者が聴者であることへの反発となっていて、地位を低く見る姿勢へと繋がっていきます。言語である以上、そこに技能があることは自明の理なのですが、手話に技能を認めない人々が設立当時には多数いました。仮にツール(道具)であっても、良し悪しや使い方のノウハウがあるのですが、「聾者とのコミュニケーションはボランティア」であり、「無償の奉仕」であって、「奉仕に上下があってはならない」という思想の人々が多数を占めていました。そういう人々は手話通訳士というプロ化にも反対していて、手話講座を修了すれば自動的に登録し、「経験を積んで、役に立つようになればよい」という主張でした。そして「初心者もベテランも同じく公平に扱われるべき」という思想でした。手話技能検定という制度は本来、手話通訳士養成と連動するものでしたが、受益団体である聾者団体は手話技能検定に反対し、妨害もありました。業務妨害として刑事事件になった例もあります。しかし現在では、その団体が全国手話検定という類似した商号で事業を行っています。そうした運動闘争とは距離をおいて、言語技能測定技術を開発し、検定試験を開始しました。英語教育では「聞く、話す、読む、書く」という四技能があるというのが定説です。しかし「手話は文字がない」ため、読む、書く、という技能はありません。聞く、の代わりに、目で見る、つまり読み取りがあり、話す、の代わりに手話表現という技能があるわけです。そして英語の四技能にも難易度の違いがあるように、手話技能にも難易度があります。英語では、読む、や聞く、より、話す、書く、の方がむずかしいです。「受容より産出がむずかしい」のです。しかし手話はどうでしょうか。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |