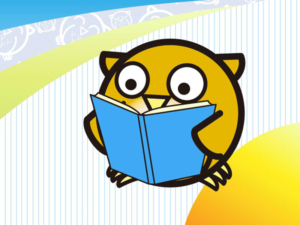言語技能測定技術と言語教育㉑ 直接法
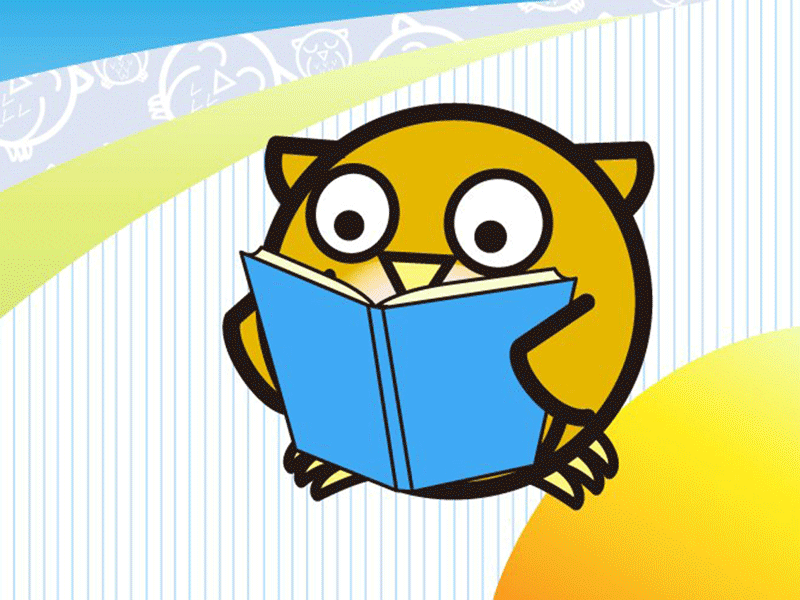
自然法の学習過程をよく観察すると、「その場で、そのものの名前を知る」という方法が多いことがわかります。これを直接法Direct Methodといいます。直接法は語学だけでなく、芸術やものづくりの世界でも「実際に見て覚える」ことがあり、幅広く応用されている学習法です。アフリカで先住民に出会ったヨーロッパ人、オーストラリアでアボリジニに出会ったイギリス人、南米大陸で先住民に出会ったスペイン人、北米で先住民に出会った英仏人など、異民族に出会った時、実物を指差して「あれは何だ?」と尋ねたことでしょう。実はこの出会いの時のゲームのような感覚が言語の起源であるという新しい言語起源論があります。外国だけでなく、日本でも、アイヌ人と接した人は同じような交渉をしたでしょう。また幕末で初めて欧州人に出会った人たちも同じことをしています。その時に聞いた音を自分の言語風に置き換えて覚えます。「耳から習う外国語」でよい方法なのですが、時には誤解も生じます。カンガルーは今ではあの動物を意味しますが、1776年,イギリス政府はジェームズ・クックを船長とした船をオーストラリアに向かわせ、そこで先住民と出会ったイギリス人は指差して「あれは何だ?」と尋ねました。アボリジニたちは「あれはgangurru(ガングルー)だ」と答えました.gangurruは現地語で「飛び跳ねるもの」という意味で,アボリジニたちはカンガルーをこのように呼んでいたので,それがそのまま英語の「kangaroo(カンガルー)」に変化したわけです。俗説に「現地語で「わからない」は「カンガルー」と発音しました.そのため,クックは「おおそうか,あの動物はカンガルーと言うのか」と勘違いをし,そのままそれを英単語にしてしまったのだ」というのがありますが、それは作り話のようです。日本でも、鉄を亜鉛メッキしたものを「ブリキ」といいますが、これは江戸の飾り職人が英国館のレンガ壁についていたランプが気に入り、通りかかった英人に聞いたところ、英人はレンガ壁のことだと思ってbricksと答えたのですが、それを聞いた飾り職人は「ブリキ」と思い込んだ、という逸話があります。南米で先住民から、タバコ、トマト、ジャガイモを教わったのですが、スペイン人はいい加減な人ばかりだったようで、適当な言葉にしてしまいました。それでtobacco, tomato, potatoというo-a-oという母音の連続に適当な子音を付けた新造語で本国に紹介しました。日本語で考えるなら、ホニャララ、ペケペケのような無意味語です。こういう例は枚挙にいとまがないのですが、こうした指差しによる直接法は誤解を生みやすいのです。また現物が目の前にあるとはかぎらない語、たとえば「友情」「真実」のような抽象語は伝えることがむずかしいです。実際、日本にやってきたキリスト教宣教師は「神」や「信者」「天国」ような概念を伝えることに相当苦労したようです。現在では漢語にうまく訳された語も多いですが、これは従来ある語の概念を利用して、外国語の概念を伝える方法で、移行transitionと呼ばれる語学技術です。日本の伝統的英語教育は移行法が中心です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |