弥生朔日
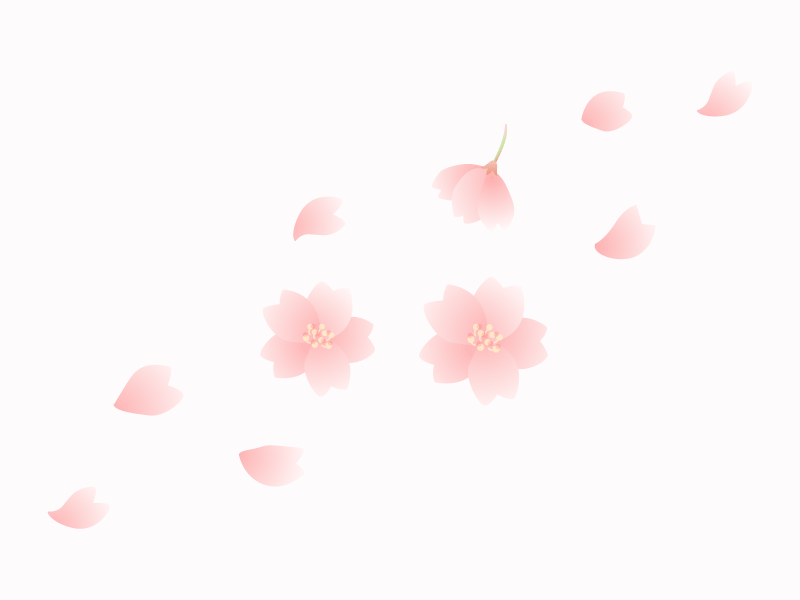
3月29日、旧暦では弥生朔日となります。今年はこの時期に桜も咲いていますから、正に春らしい時期となりました。まだ時々寒い日もあるかと思うと、初夏を思わせる暑い日もあって、これも春らしい気候です。この気温の寒暖差によって、空気中の水分が霞や霧になるので、それがまた春らしい景色となります。
枕草子の有名な序である「春はあけぼの。春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく、山ぎは少し明りて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。」の時期は、もう少し早い早春の頃だそうで、夜明け前の状態を描いたものだそうですが、時節をそれほど厳しく限定する必要もなく、また原文は京の様子を描写したものですが、日本の各地域に広げて、味わってもよいのではないかと思います。現代風にいえば「緩い」ということになりますが、季節感というものは地域や個人、年によって違っている曖昧なものですから、各自がそれぞれの思いで味わってよいものだと思われます。
弥生も30日間あり、朔日と月末では気候もまったく変わります。旧暦の1月は二十四節気より長いので、気候が変わるのも当然です。1年は春夏秋冬の四季に分けられ、12カ月に分けられています。二十四節気や七十二候は細かい分類になっていて、微妙な季節変化や自然の変化をとらえて、美しい言葉で表現しています。それこそ日本の伝統であり文化ですから、それを味わう感性を育むような教育もあってよいと思われます。これには自然観察をする目を持てるだけでなく、表現や漢字も勉強できるという利点もあります。古典や文学作品を学ぶことには意義がありますが、子供にとっては長すぎるという弱点もあります。七十二候程度であれば、短く身近な現象であり、また時代の変遷も学べるので、手軽だと思われます。そして古典や文学の中には、こうした季節感を表現した例も多いので、より深い学習のための基礎として必要な知識でもあります。日本文化の学習機会の1つとしてもよいと思います。
さて、弥生という月名は、「弥」は「ますます」という意味で、「生」は「草木が生い茂る」という意味です。語源は「木草弥や生い茂る月」(きくさいやおいしげるつき)が短くなって、「いやおい」となり、それがさらに短くなって「やよい」になったそうです。(https://jpnculture.net/yayoi/)昔から、日本語は省略することが好きなのですね。「明けましておめでとう」が「あけおめ」になったり、「メリークリスマス」が「メリクリ」になる若者語の省略法則は、実は古典的な語法の踏襲なのです。省略というのは、当初は、元が何であるのか想像できないといけないものなのですが、長く使われているうちに元がわからなくなり、省略語が1つの語として定着していきます。言語はこのように進化していく「生き物」なのです。月名(異名)には月がつくものと、つかないものがありますが、元は全部ついていたのが省略する過程でなくなったと考えられます。今は数字の順番だけで、便利かもしれませんが、味気ない気もします。英語を含む欧米では今も伝説の神名のままです。なんでも欧風を採り入れた明治維新や戦後改革にしては珍しい現象です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


