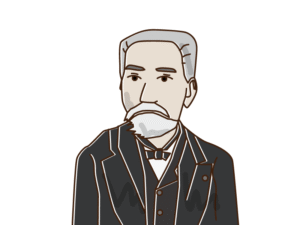高血圧の日
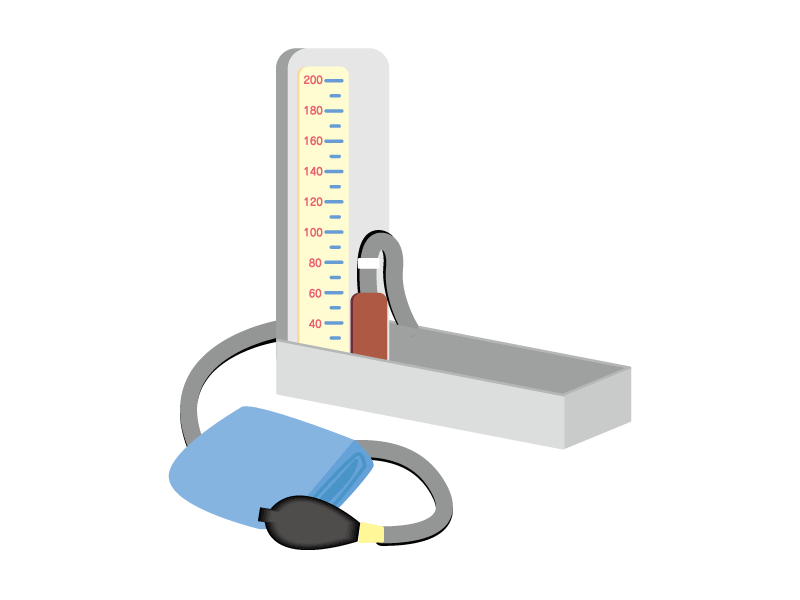
2007年5月17日の「世界高血圧デー」を中心に実施された高血圧の啓発活動が、2008年からは日本でも正式に高血圧の日として、日本高血圧学会と日本高血圧協会が、第30回日本高血圧学会総会において、毎年5月17日を「高血圧の日」と制定しました。
高血圧(140/90 mmHg以上)は、日本人の三大死因のうちの二大疾患である脳卒中や心臓病など、生命に関わる病気を引き起こす最も主要な原因となっています。しかし、高血圧はサイレント・キラーと呼ばれるように、自覚症状がないために、現在、日本に約4,000万人と推定されている高血圧患者のうち実際に治療を受けているのはわずか2割の約800万人といわれています。高血圧治療ガイドラインで定められている血圧目標値および至適血圧値は、75歳以上では150/90mmHg未満、可能であれば140/90mmHg未満を目標にする。75歳未満は140/90mmHg未満、蛋白尿を伴った慢性腎臓病・糖尿病を合併している患者は130/80mmHg未満で、至適血圧値は120/80mmHg未満とされています。
日本の基準は値が低すぎるという意見もありますが、アメリカの高血圧ガイドラインは、アメリカ心臓協会(AHA)と米国心臓病学会(ACC)の共同により、最近の改定では、年齢ではなく、血圧の分類は、正常、高血圧前期、ステージ1高血圧、ステージ2高血圧の4つに分けられています。正常は120/80 mmHg未満、高血圧前期は120-129/80 mmHg未満、ステージ1は130-139/80-89 mmHg、ステージ2は140/90 mmHg以上と定義されています。
ヨーロッパの高血圧ガイドラインは、南北のヨーロッパの国々での高血圧の管理と予防において重要な指針を提供しています。特に、2018年に発表されたガイドラインは、血圧値のカテゴリー分けや、患者に対する治療法を詳細に示しています。一般的に、収縮期血圧が140 mmHg以上、あるいは拡張期血圧が90 mmHg以上の場合は、高血圧とみなされます。
こうしてみると、日本の高血圧基準がとくに低いということではなさそうですが、テレビCMなどでは130mmHg以上という情報が流れているので、それだとやや低いということはいえます。体調は個人差も大きいので、どの指針でも、判断基準として公開されているわけです。この基準を超えた場合は、医療機関に相談した方がよい、というわけです。血圧は一日の間でも変化しますし、運動後、食後、精神的な状況でも大きく変化しますが、常に高い状態というのは何かの異常があります。血圧だけで断定はできないので、他のいろいろな検査をして、病気があれば発見することが重要なわけです。とくに心臓や血管に異常がある場合はより深刻で、死亡原因ですから、早めの受診と治療が大切になってきます。
高血圧症の原因の多くは動脈硬化で、その原因は加齢、生活習慣、長期ストレスとなっていて、これもよく知られています。しかし現実には、加齢は避けようがなく、ストレスもなかなか解消がむずかしいので、生活習慣を変える、という対策になりそうです。薬に頼らず、規則正しい生活と適度な運動と栄養バランスを考えた食事、という「当たり前のこと」が結論になります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |