役行者(えんのぎょうじゃ)と寛政異学の禁
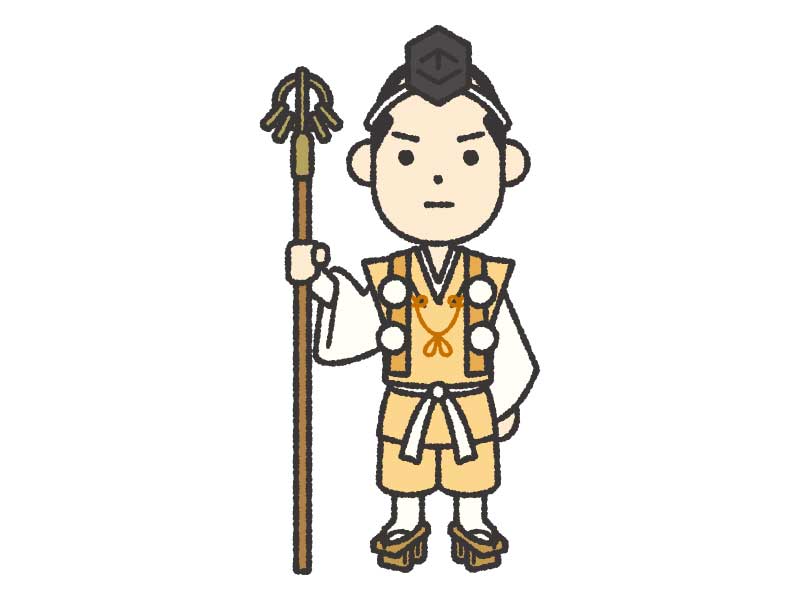
旧暦5月24日は、修験道の開祖とされる「役の行者(えんのぎょうじゃ)」こと役小角(えんのおづぬ)の縁日とされています。修験道は、日本古来の山岳信仰に仏教や道教の要素が融合した独特の宗教体系であり、役の行者はその象徴的存在です。この日は、全国の修験道に関わる寺社で法要や儀式が行われ、信仰を集めてきました。役の行者は飛鳥時代の人物で、実在したとされるものの、その生涯には神話的要素が多く含まれています。奈良時代の歴史書『続日本紀』によれば、小角は超人的な呪術を操り、山中で修行しながら霊力を高め、多くの人々を導いたとされます。しかし、彼は時の朝廷に疎まれ、「人心を惑わした」として流罪に処されています。この逸話は、後の修験道の修行者たちにとっては象徴的な教訓ともなり、「権力に抗う霊的存在」としての役の行者像が形成されていきました。小説や漫画の題材にもなっています。
江戸時代に入ると、幕府は宗教に対する厳格な統制を行うようになります。仏教は幕府公認の寺院制度に組み込まれ、民衆管理の手段とされました。その一方で、民間信仰や異端的思想への警戒も強まりました。その象徴的な政策の一つが「寛政異学の禁」です。寛政異学の禁は、寛政5年(1793)、老中松平定信によって発布された政策で、幕府が朱子学以外の儒学、特に陽明学や古学の講義・教授を禁止したものです。この背景には、陽明学が内面の良知や行動を重視する思想であり、体制批判に繋がりやすいという懸念がありました。幕府は朱子学を「統治に都合の良い正学」と位置づけ、教育と思想の統一を図りました。つまり、民衆だけでなく知識層にも「考える自由」を制限したのです。この政策は思想的多様性を奪い、後の幕末に至るまで武士階層に深い影響を与えました。陽明学者の中には地下に潜り、密かに学問を伝えた者もいました。例えば、吉田松陰など幕末の志士たちは陽明学の影響を強く受け、幕府体制を批判する思想的支柱となっていきます。つまり、寛政異学の禁は短期的には統制を強めましたが、長期的には体制変革の火種を養う結果にもなったのです。
ここで改めて、旧暦5月24日の役の行者の話に戻りましょう。彼が受けた弾圧と、その後に信仰の対象として復活した歴史は、日本社会において「異端」とされた者がやがて正統の中に取り込まれていく逆説を示しています。役の行者もまた、一時は「妖術使い」とされ流罪にされたにもかかわらず、後には国家公認の聖者として、神仏習合の文脈で祀られるようになりました。寛政異学の禁と修験道の歴史は、一見無関係に思えるかもしれませんが、どちらも「思想と言論、信仰の自由」をめぐる日本の政治と宗教の関係を象徴しています。いずれの場合も、国家が「正しい」と定めた思想や信仰以外は「異端」とされ、排除の対象となりました。しかし、そうした異端の思想や信仰が、のちに時代の転換期を生み出す原動力になったことは歴史の皮肉でもあります。現代の私たちは、歴史を通して思想や信仰の自由の大切さを学ぶことができます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


