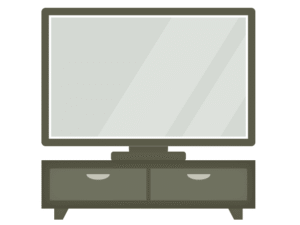梅干しの日

毎年7月30日は「梅干しの日」です。この記念日は、単なる食材としての梅干しを讃える日ではなく、日本人の生活文化や健康観、さらには自然との調和を象徴する記念日でもあります。「梅干しの日」は、和歌山県みなべ町の「紀州梅の会」によって制定されました。日付の由来は、「梅干しを食べると難が去る」という言い伝えに基づき、「なん(7)」「さ(3)る(0)」と語呂合わせされ、7月30日とされました。この洒落の効いた発想は、古来より語呂合わせや季節の言葉遊びを大切にしてきた日本人の感性をよく表しています。梅は、奈良時代以前から日本に伝わる薬用植物とされてきました。『万葉集』にも梅の花が詠まれており、その美しさと同時に薬効の高さにも注目されていました。梅を塩漬けにし、赤紫蘇とともに漬け込んだ「梅干し」は、保存性に優れ、戦国時代には兵糧として重宝されていた記録もあります。とくに豊臣秀吉が軍陣で梅干しを配給させ、兵士の健康を守ったという逸話はよく知られています。また、江戸時代には梅干しが庶民の常備薬として認識され、解毒や殺菌、夏の食欲不振の予防に活用されてきました。このように、梅干しは食材であると同時に、薬としての役割も担っていたのです。
日本の伝統的な朝食を思い浮かべたとき、ご飯、味噌汁、焼き魚、そして梅干しを思い出す方も多いのではないでしょうか。梅干しは、ご飯の酸化を防ぎ、食中毒予防にも一役買ってきました。また「日の丸弁当」と呼ばれる、白いご飯の中央に一粒の梅干しを置いた弁当は、視覚的な美しさと合理性を兼ね備えた代表的な和食文化の象徴です。赤い梅干しは「魔除け」の意味も込められ、見た目以上に深い意味が込められているのです。
近年では、梅干しに含まれるクエン酸やポリフェノールなどの成分が注目され、疲労回復、抗酸化作用、抗菌作用、整腸作用など、さまざまな健康効果が科学的に証明されています。また、塩分を控えめにしつつも、しっかりと酸味を残す製法が求められるようになり、現代人の健康意識とともに進化してきた食品ともいえるでしょう。とくに、近年では「梅干しを1日1粒食べると医者いらず」とも言われるほどで、海外からもその健康効果が注目され、「UMEBOSHI」という言葉がそのまま商品名として輸出される例も増えています。
梅干しは、初夏に収穫される梅の実を塩漬けし、土用の丑の日あたりの強い日差しで「土用干し」を行うという、季節との調和が色濃く現れた食品です。梅雨の終わりから夏の盛りにかけて仕込まれる梅干しは、まさに日本の気候に寄り添った保存食であり、季節のリズムを感じさせてくれる食文化でもあります。また、この「土用干し」を行う時期には、家族総出で梅を干すという風習も残っており、食を通じた家族の絆も見直されます。冷蔵技術が発達し、加工食品が溢れる現代にあっても、梅干しの価値は衰えることがありません。むしろ「伝統回帰」「自然志向」といったライフスタイルの中で、梅干しのような発酵食品や保存食の持つ力が再評価されています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |