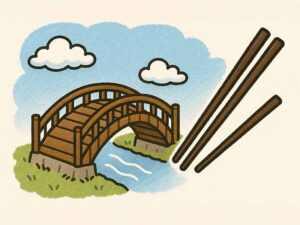「ハチミツの日」と「ハサミの日」

8月3日は日本の文化や暮らしの中に深く根ざした2つのユニークな記念日が存在します。それが「ハチミツの日」と「ハサミの日」です。どちらも語呂合わせから生まれた記念日ではありますが、その背後にはそれぞれの道を究めた人々の思いや、日本人の生活と文化に対する深い関わりが見えてきます。
「ハチミツの日」は、1985年に全日本はちみつ協同組合と日本養蜂はちみつ協会によって制定されました。8(はち)3(みつ)の語呂合わせです。この日には、養蜂業の理解促進やハチミツの利用促進、そして自然環境保全への啓発活動が行われています。ハチミツは、古代エジプトやギリシャの時代から神聖な食品として用いられ、滋養強壮や保存食品、あるいは傷の治療にも使われてきました。日本においても、古代よりミツバチと人との共存は続いており、戦後には養蜂業が近代化され、農業や果樹栽培との連携が進みました。近年では、自然食品や健康志向の高まりとともに、国産ハチミツの価値が見直されています。特に「百花蜜」や「アカシア蜜」「レンゲ蜜」など、日本の花と風土に育まれた多様なハチミツの風味は、味覚だけでなく季節や土地の記憶をも呼び起こす特別な存在となっています。また、ハチミツは単なる甘味料ではなく、抗菌性や保湿性を活かして、スキンケアや喉のケアなど幅広い健康分野にも応用されています。この「ハチミツの日」を通して、自然の恵みと私たちの暮らしとのつながりを再確認する機会にもなっているのです。
一方、「ハサミの日」は、1978年に美容師の草分けとして知られる山野愛子氏が提唱した記念日です。同じく8(は)3(さみ)の語呂合わせです。この日は、美容師や理容師、洋裁師など、ハサミを仕事道具とする人々が、使い古されたハサミに感謝し、供養する日として位置づけられています。日本には古くから、道具に魂が宿るという「付喪神(つくもがみ)」の思想があります。長く使った道具には心が宿るとされ、特に刃物や筆、針などの精密な道具には特別な意味が与えられてきました。これに基づき、使い終えたハサミを神社などで供養し、その役割に感謝する「ハサミ供養」が行われています。また、ハサミは単なる道具ではなく、「切る」という行為に象徴されるように、何かを分ける・整える・清めるという精神的な意味も持ちます。美容師にとってはお客様との信頼をつなぐ道具であり、洋裁師にとっては形を創り出す手段でもあります。そのような大切な道具に対して「ありがとう」と感謝を伝える文化は、現代においてこそ見直されるべき心のあり方といえるでしょう。
「ハチミツの日」と「ハサミの日」は、いずれも語呂あわせですが、単なる遊び心だけでなく、自然や道具、人の営みに対する感謝と尊重の精神が根底にあります。現代社会では、便利さやスピードばかりが重視されがちですが、このような記念日をきっかけに、私たちの生活を支えてくれているものに目を向けるのは、持続可能で心豊かな社会を築くうえで欠かせない視点です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |