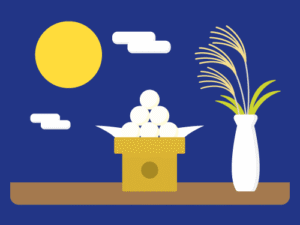手話の雑学34

類人猿の手話習得の研究は手話の言語起源論に拍車をかけました。そして、もう1つ、傍証となっているのが、幼児の言語習得過程です。
幼児は生後12か月頃までは言語音声を発声できません。しかし、身振りに近い手話であれば、7カ月前後で獲得できることがわかってきました。人間の発達は、精子と卵子の結合から、細胞の分裂を繰り返し、その発達過程は、人類の発達過程を追いかけているように見えます。胎児の姿は魚に似ていたり、爬虫類に似ていたりする段階を経て、出産前にほぼ人間の形になります。しかし、人間の幼児は、他の哺乳類の動物に比べて、「未熟児」の段階で出産されます。動物の場合は、生後すぐに立ち上がって歩行し、授乳できます。しかし、人間の幼児は二足歩行までに1年近く、言語がそれらしくなるまでに3年近くかかります。もし、人間の最大の特徴が二足歩行と言語使用にあるならば、未熟児出産が普通ということになります。その理由はいろいろ考えられていますが、脳の拡大が原因ということが言われています。また、類人猿の場合、二足歩行は可能ですが、四足歩行が多いのですが、手の使用はほぼ自由であること、また道具の使用もあることも、この人間の発達過程に1つの説明仮説が可能になります。つまり、類人猿から、人間に分かれる過程で、突然、言語習得があった、と考えるよりは、進化段階で、徐々に言語能力が形成されていった、と考えるわけです。
ただし、進化論でよくある誤解は、猿が進化して人間になった、というオモシロ話です。猿は今後いくら進化しても人間にはなりません。進化論が説明しているのは「共通祖先」という考えです。猿と人間の祖先は同じで、それから進化していく過程で分離していったということです。これは「系統樹」という表を見ればわかります。この系統樹によれば、ヒトは現代人に至る前に、いくつかの分化があり、旧人類と新人類だけでなく、ヒト科の分化過程については、DNAの研究などが今も続けられています。どの段階で言語能力を得たのか、ということは、いろいろな視点からの研究を統合しないといけないので、まだ未完成ですが、そもそも「言語とは何か」がきちんと定義されないと、分岐点が決められません。議論がまた元に戻ってしまいますが、「言語とは何か」という昔からの議論が再燃します。たた、同じ議論が続くのではなく、新たな証拠が加わったことで、より精緻な議論ができるようになりました。チョムスキーが提唱した「言語習得装置」についても、脳科学や遺伝子研究によって、ある程度わかってくる日も近いかもしれません。
この言語進化論を考える上で重要なことは、手話から音声言語に進化したことが、「手話が音声言語より原始的」と考えるのは誤りであるということです。たとえば「仮名は漢字から発達した」ことがわかっていますが、仮名よりも漢字が原始的と思う人はいないでしょう。そもそも文字は話しことばから発達したものですが、話しことばは原始的という人はほぼいないと思われます。
「ほぼ」としたのは、文字による書類は、話したことよりも価値が高いと思う人がいるからです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |