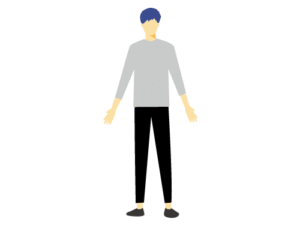手話の雑学61

日本語文法の説明だけから手話の品詞を分類することは不可能です。つまりより一般文法的な技法が必要であり、「名詞の文法機能」「動詞の文法機能」という、より専門的な観点から考える必要がでてきます。その原因は音声言語では、語という単位がわかりやすく、語は形態素からできている、という構造が簡単に示すことができますが、「手話では、語と形態素の境界が曖昧」という点です。
みなさんの頭の中は学校文法という旧世代の文法論なので、まずは現代文法の基礎知識について、考えてみます。現代文法の分類は、単なる「言葉の種類分け」ではなく、文の構造や意味の組み立て方を明らかにするための道具です。言い換えれば、言語を「意味」と「構造」の両面から科学的に捉えるための分析フレームです。現代文法では、品詞の分類は「文節」や「形態素」という単位と関わりながら整理されています。伝統文法よりも構造的・機能的な視点を重視するのが特徴です。現代日本語文法では、文節と形態素という単位を考えます。文節は、日本語文法の中で意味とリズムの最小単位です。たとえば、「私は / リンゴを / 食べます」という文は、3つの文節に分けられます。それぞれの文節の中で、さらに最小の意味・機能の単位に分解したものが形態素です。「食べます」を分けると、「食べ(動詞の語幹)」+「ます(助動詞)」という二つの形態素になります。つまり、文節とは、意味のかたまり(話しことばのリズムの単位)であり、形態素は、文法的に最小の単位(これ以上分けられないもの)ということになります。現代日本語文法では、形態素を中心にして次のように分類します。
(A)自立語:文節の中で中心的な意味をもつ語。単独で文節を作れる。
名詞:ものの名前。例:人、学校、愛
動詞:動作や変化。例:走る、食べる、ある
形容詞:「〜い」で終わる性質語。例:高い、早い、うれしい
形容動詞:「〜だ」で述語になる性質語。例:静かだ、元気だ
副詞:主に動詞・形容詞を修飾。例:とても、ゆっくり
連体詞:名詞を直接修飾。例:この、大きな、ある
接続詞:文と文をつなぐ。例:そして、だから、しかし
感動詞:呼びかけ・応答など。例:ああ、はい、もしもし
(B)付属語:自立語にくっつき、文法的な関係を示したり意味を補ったりする。
助詞:語と語、文と文の関係を示す。例:が、を、に、は、の、まで、など
助動詞:動詞や形容詞の後に付き、意味を加える。例:〜ます、〜たい、〜られる、〜だろう
ここまでは大丈夫でしょうか。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |