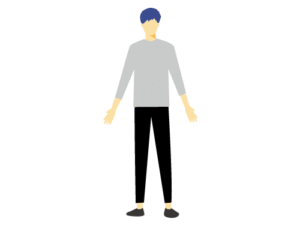手話の雑学62

現代日本語文法の続きで、次は文法的視点です。機能的な視点(述語中心の構造)として、現代文法は「文の中心=述語」と考えます。
「雨が降る」→ 述語「降る」に主語「雨が」が対応。
「リンゴを食べる」→ 述語「食べる」に目的語「リンゴを」が対応。
この構造的関係を分析することで、文節の役割(主語・述語・修飾語など)を明確にします。助詞はこの関係を示す「文法マーカー」として重要です。「が」「を」「に」などは、名詞がどんな機能を持っているかを決める“接着剤”のような存在です。
さらに、ここからがややむずかしいのですが、形態論的観点です。
形態素は、さらに「語幹」と「語尾」に分けられます。
動詞「書く」→「書(語幹)」+「く(語尾)」
形容詞「高い」→「高(語幹)」+「い(語尾)」
語尾の変化(活用)が文法的役割を担うため、日本語文法では「活用のある品詞(動詞・形容詞・形容動詞)」と「活用のない品詞(名詞・副詞・助詞など)」の区別が非常に重要です。
これが現代日本語文法のあらましです。自然言語処理などの情報処理の世界では、この現代文法が使われています。日本手話文法を考える上で、日本語文法独自の要素はず除いて、どの言語にも通用しそうな「一般言語学」の用語を基本に考えていきます。「文節」と「形態素」は使えそうな気がしますが、日本語と対応しているとはかぎりません。文節はリズムが判定基準に使われるのですが、手話にリズムがあることはわかっています。音声言語なら「息つぎ」で文節が直観的にわかりますが、手話でも手話者なら、間(ま)の置き方や、瞬き、頷きなどでリズムが作られていると感じます。実際の研究はそれほど進んではいませんが、「文節マーカー」の実態については、これから次第にわかってくると思われます。形態素についても、あらましが分かってきています。形態素損でいう「語幹」と、「語尾」つまり接辞です。語尾という表現は日本語のように形態素の配列順序が決まっている場合はよいのですが、手話のように「同時に」表現される場合には不適切です。そこで、語尾の代わりに同じ概念である「接辞」という用語を用いることにします。日本語文法では「活用」つまり語形変化のあるなしが、語幹と語尾の違いとされていますが、同じように日本手話では、形の変化のあるなしで、識別してみてはどうか、という提案です。たとえば「会う」という手話表現では、「立てた人差し指」と「接近する」は変化しませんが、位置が変化します。従来の手話学の用語を使えば、手型と動きは変化せず、位置が変化する、ということです。そこでたとえば、日本手話の「会う」の構造は仮に、「人差し指が接近する」を語幹、位置による人称変化を接辞と考えてみてはどうでしょうか。これが形態論的視点です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |