独身の日
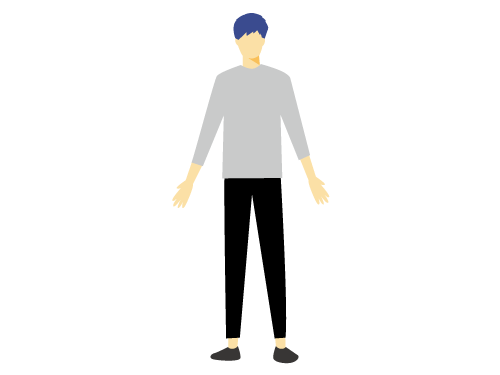
本日は1が並ぶということで、中国では「独身の日」だそうです。日本ではまだなじみの薄い習慣ですが、アジアの経済・文化圏ではすでに一大イベントとして定着しているそうです。そもそもこの「独身の日(光棍節)」という名称は、1990年代の中国の大学生たちの間で生まれたものだそうです。1が並ぶ日を「一本立ち=独り身」と見立て、独身者同士が自分たちの存在を祝おうという、ささやかなユーモアから始まりました。恋人や家族のいない人々が、さびしさを笑い飛ばす日だったのです。韓国では、バレンタインデーの翌々月にイエローデーというのがあって、プレゼントがもらえなかった同士があつまってカレーを食べるそうです。これと似た発想なのでしょう。
ところが、時代が進むにつれて、この「独身の日」は一種の逆転現象を起こしました。2000年代に入ると、中国のネット通販大手アリババが、この日を大規模セール「双十一」として打ち出します。恋人のいない人が自分へのプレゼントを買う、という発想から始まったキャンペーンは、瞬く間に巨大な商業イベントへと変貌しました。いまでは世界最大級のオンラインショッピングデーであり、アメリカの「ブラックフライデー」をも上回る売上を記録する年もあります。
数字の並びが作った冗談のような記念日が、経済を動かす日へと変わったのは、まさにデジタル時代の象徴です。SNSやECサイトの発達により、人々は同じ日に同じキーワードでつながり、同じ行動をとるようになりました。かつて「孤独」を表していた1が、いまや「共鳴」を生み出す符号になっているのです。
一方で、この現象は現代社会のもう一つの側面も映し出しています。それは、「個人消費の時代」ということです。誰かに贈るためではなく、自分のためにお金を使うことが、肯定されるようになりました。独身の日のセールには、「恋人がいなくてもいい、自分を満たせばいい」というポジティブなメッセージが込められているとも言えます。中国では「自分へのご褒美消費」が文化的にも浸透し、若者たちは「他者に合わせるより、自分の好みを貫く」ことを選び始めています。
この流れは日本でも共感を呼びつつあります。たとえば、ひとり旅、ひとり焼肉、ひとりカラオケなど、かつては「寂しい」と見られがちだった行動が、今では「自由で贅沢な時間」として受け入れられています。「独身の日」は、そうした価値観の変化と響き合う日でもあるのです。
もっとも、この日が完全に祝祭的なものかというと、そこには微妙な感情も混ざっています。社会の構造や世代の意識のなかで、結婚をめぐる価値観が多様化し、「独身」という生き方が再定義されているからです。結婚をしないこと、子をもたないことが、もはや「例外」ではなく「選択」として語られるようになりました。数字の「1」は、孤立ではなく、独立を意味するようにもなっているのです。一方で、SNS上では「恋人がいない日」や「ぼっちの日」として、自嘲気味に盛り上がる人々の姿もあります。笑いの裏にあるのは、他者とのつながりを求める心でしょう。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

