言語技能測定技術と言語教育理論① 言語変種
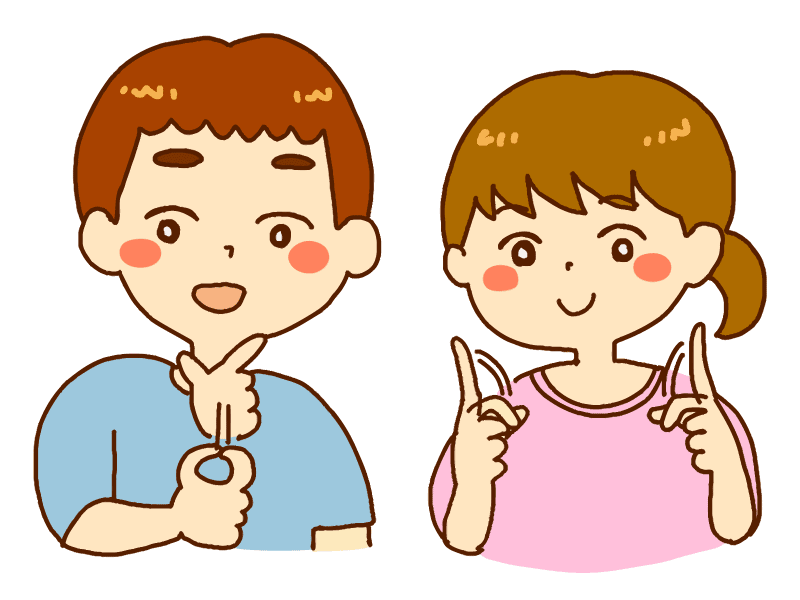
言語使用の技能として、受容技能よりも産出技能の方がむずかしい、ということは英語を習った経験から実感できます。しかし手話学習では、手話をすること(産出)よりも、読み取り(受容)の方がむずかしい、という話をよく聞きます。これはなぜでしょうか。英語教育の場合、文字を用いた「読み」つまり英文解釈と「書き」英作文では、確かに英作文が苦手の人がほとんどです。英会話においても、聞き取り(聴解)と発話を比べると、「うまく話せない」というケースがほとんどです。「言ってることはなんとなくわかる」けれど「どう答えたらいいのかわからない」のがよくあるケースです。ここに手話教育の特殊性があるのですが、一般だけでなく専門家も理解していません。理由を答えられる人はほとんどいないのではないでしょうか。本当はかなり詳しい言語学的説明が必要なのですが、簡単に説明すると、英語の場合、日本人が習っている日本英語と、相手が使用する国際英語またはアメリカ英語などとの差があまり大きくないといえます。後述しますが、母語話者(ネイティブ)の受容能力は高く、間違いや不正確であっても理解できる範囲は広いのです。日本人の日本英語でも、話せばほぼ理解できます。日本人も日本英語で話してもらえば聴解も簡単です。国際英語は日本英語に近いので、英米人の英語よりも、非英語圏の人の英語なら聞き取りやすいのは、それが原因です。国際英語というのは1つの英語ではなく、世界に存在する英語World Englishesのことで、世界の各種の英語がすべて含まれる概念です。日本英語も実はその1つに入っています。こういう言語同士の関係をまず理解すると、その後の英語学習も進みやすくなります。同じように、手話について、いわゆる日本手話にも、使用者によって違いがあります。これを言語変種といいます。日本手話という総称の中に、聾者と呼ばれる人々が伝承してきたと考えられる手話、昔は伝統的手話と呼ばれる変種と、手話通訳が登場するようになって急速に発展してきた、主として聴者が使う手話、いわゆる聴者手話があります。聴者手話を「日本語対応手話」と呼ぶ人もいますが、この概念は曖昧なので、注意する必要があります。聴者手話の中にも変種があり、手話学習初心者が使う「指文字だらけ」のものから、手話通訳士のようなプロが使う高度なものまであります。昔は、ろう者手話、日本語対応手話、中間型手話などの分類が行われましたが、現状のように複雑になっていると、こうしたざっくりとした分類ではなく、使用者別に分けたり、場面によって分けるなどの詳細な分類が必要になっています。聾者手話も世代による違いが顕著になってきており、とくに聴者との交流が進んできて、「新しい手話」を母語とする世代がいます。近年、SNSなどの影響も強くなり、独特の用法を聴者と共有する世代も増えて、古い世代からすると「日本語化」が進んだ聾者手話も増えています。手話通訳の手話も、高齢の聾者と聴者で共有する変種もあれば、若い世代で互いに共有している変種もあり、単純に聾者と聴者という使用者分類では間に合わない状況になっています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |


