彼岸の菓子
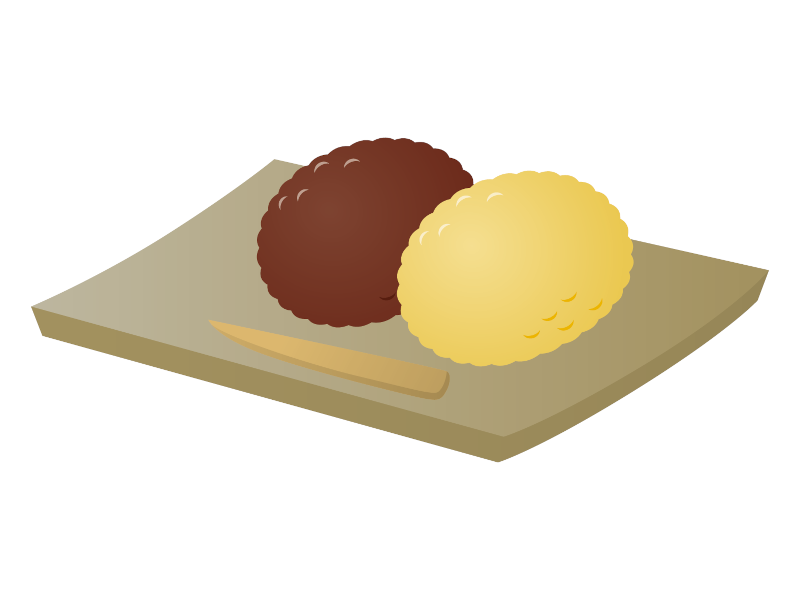
春の彼岸の代表的な食べ物は「ぼたもち」ですが、他にも季節の野菜やきのこを使用することが最適とされており、春彼岸にはタラの芽やたけのこ、秋彼岸にはきのこやナスなどを食べます。 お彼岸の食事には、いなり寿司や五目寿司が定番の一つです。 古くからの儀礼として、山菜やれんこんの酢漬けを使って、肉や魚を避けて作られています。 仏教の教えでは、生命を宿す動物をお供えすることが禁じられているためです。植物にも生命がある、という理屈もありますが、仏教では動物だけを対象と考えています。これはビーガンと呼ばれる菜食主義者にも当てはまり、古今東西、「動く」ということが生命の証と考えているわけです。もっともさらに屁理屈をいえば、植物にも動きがあり、花が咲いたり、実をつけるのも動きがあります。要するに真理であるかどうかの議論ではなく、「教えとして信じる」ことが重要なのです。それも宗教というような大げさなものではなく、文化であり習慣であるにすぎません。春彼岸には三色のお彼岸団子を食べる風習のある地域も多く存在します。お彼岸にお団子をお供えする意味には諸説あります。「長い旅路にお疲れの故人様を癒すため」、「地上のものを食べることで、故人様との繋がりを感じるため」あるいは「再び極楽浄土へとお戻りになる故人様への敬意を表すため」というものです。また、日本には仏教が伝わる以前から、ご先祖様が自然に日々不自由なく生活できることへの感謝や敬意を表す習慣がありました。それが、お彼岸に感謝や敬意を表すようになったとされています。里芋が主食だったころ、お彼岸団子も里芋がお供えされていたといたそうです。しかし、里芋は時期によって手に入らない場合もあり、そのような時期には里芋に見立てた団子をお供えしていました。あの丸い形は里芋の真似たものだったのですね。その後、時代とともに主食が里芋からお米となり、お供えものもお米に変わっていきました。そして牡丹餅(ぼたもち)やおはぎ、故人様の好きなものなどをお供えするようになりました。しかし、地域によっては団子をお供えする風習が残っている場所もあり、お彼岸に団子をお供えするのはこのためとされています。お彼岸に団子をお供えする数は地域や家庭ごとに異なるため、明確な決まりはありません。お供えする団子の数によって意味が異なります。6個の場合、仏教では死後、「地獄」「餓鬼(がき)」「畜生」「修羅」「人間」「天上」の六道(ろくどう/りくどう)を輪廻転生するといわれています。この六道にちなんで、お彼岸団子は6個が一般的とされています。7個の場合もあり、「六道の輪廻転生から抜けて極楽浄土へ行けるように」という思いから、7つの団子をお供えするようになったといわれています。仏教では死後、亡くなられた日から7日ごとに六道のうちのどの世界に生まれ変わるかを決める裁判がおこなわれると考えられています。この最初の裁判が「初七日」、最後の裁判が「四十九日」です。このことから7個の団子をお供えするようになったともいわれています。あの三色の団子は本来は「花見団子」なのですが、時期が重なるため混同されています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


