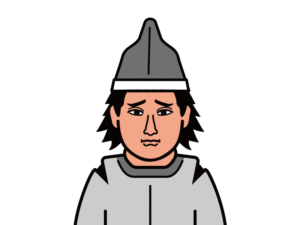蓮如の示寂(しじゃく)

明応8年(1499)3月25日(旧暦)浄土真宗中興の祖である蓮如が85歳で示寂しました。示寂というのは、高僧が亡くなることをいいます。蓮如(れんにょ)は室町時代の浄土真宗本願寺派第8世宗主・真宗大谷派第8代門首です。大谷本願寺住職。本願寺では蓮如上人と尊称されています。真宗大谷派では「蓮如」と表記するのが正式だそうです。
父は第7世存如です。親鸞の嫡流とはいえ蓮如が生まれた時の本願寺は、青蓮院の末寺に過ぎなかったのです。他宗や浄土真宗他派、特に佛光寺教団の興隆に対し、衰退の極みにありました。その本願寺を再興し、現在の本願寺派・大谷派の礎を築いたことから、「本願寺中興の祖」と呼ばれています。
浄土真宗には西本願寺派と東本願寺派があります。西本願寺は親鸞の教えを中心に広く信仰され、歴史的な影響力を持っています。西本願寺派は、浄土真宗の伝統を重んじ、法然上人の教えを中心に守っています。東本願寺派は、独自の修行方法や組織体制を持っています。東本願寺は蓮如の教えを通じて江戸時代に大きな政治的な力を持ちました。浄土真宗は、浄土宗の開祖・法然の弟子である親鸞が教えを広めたものを、後に弟子が宗教として独立させた宗派です。
蓮如は応永22年(1415)、京都東山の生誕当時に天台宗青蓮院の末寺であった大谷本願寺(現在の知恩院塔頭崇泰院〈そうたいいん〉付近)で、本願寺第7世存如の長子として生まれ、母は存如の母に給仕した女性と伝えられていますが詳細は不明だそうです。一説には、信太(現在の大阪府和泉市)の被差別部落出身だったともいわれています。(wikipediaより)
永享3年(1431)17歳の時中納言広橋兼郷の猶子となって青蓮院で得度し、実名を兼郷の一字を受け兼壽、仮名を兼郷の官途名である中納言と称し、法名は蓮如と名乗りました。その後、本願寺と姻戚関係にあった大和・興福寺大乗院の門跡経覚について修学。父を補佐し門末へ下付するため、多くの聖教を書写しました。永享6年(1434)『浄土文類聚鈔』が、蓮如により書写された現存する最古のものです。
永享8年(1436)、祖父の第6世巧如が住持職を父に譲り、4年後の永享12年(1440)に死去しました。嘉吉2年(1442)に第1子(長男)順如が誕生しました。親鸞以降、浄土真宗の僧は妻帯します。康正元年(1455)最初の夫人、如了尼が死去しました。蓮如は妻の死別を4回に渡り経験し、生涯に5度の婚姻をしました。子は男子13人・女子14人の計27子を儲けています。
長禄元年(1457)、父の死去に伴い本願寺第8代を継ぎます。しかしすんなりと世襲になったのではなく、留主職(本願寺派の法主)継承にあたり、異母弟蓮照を擁立する動きもありましたが、叔父の如乗の主張により蓮如の就任裁定となったという経緯です。なお、歴代住職が後継者にあてる譲状の存如筆が現存しないことから、この裁定は如乗によるクーデターともされています。
当時の本願寺は多難で、天台宗青蓮院の一末寺に転落しており、比叡山延暦寺からは、弾圧が加えられ、これに対して蓮如は延暦寺への上納金支払いを拒絶するなどしました。その後は宗派改革に邁進しました。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |