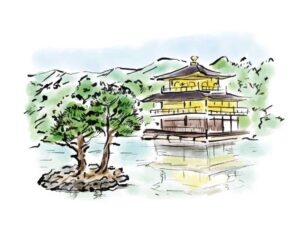三世一身法

養老7年(723) 三世一身法が発布されました。今では何でもないような感覚で受け止められるようですが、農地というものは個人所有でなく、領主のもの、あるいは国家のもの、という考えは未だに広く世界に広がっていることを思うと、当時の日本は画期的であったといえます。
「三世一身法(さんぜいっしんのほう)は、奈良時代前期の養老7年4月17日(旧暦)に発布された格(律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。8世紀初頭の日本では班田収授法に基づき、6年ごとに班田(農地の分配)が行われた。そのため、分配された農地は6年で収公され、期限が近づくごとに農地が荒廃した。また開墾者の権利が明確に定められず、国郡司が墾田を恣意的に収公することもあった。そのため、開墾者の意欲が低下しており、このような背景で三世一身法が発布された。灌漑施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合は、三世(本人・子・孫と、子・孫・曾孫とする説がある)までの所有を許し、既設の灌漑施設(古い溝や池を改修して使用可能にした場合)を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す。開墾地の面積制限はない。三世一身法は農地の収公を停止するものではなく、遅らせるだけだったので、開墾促進の効果が上がらなかったとされる。また農地開墾が裕福な貴族、神社、寺院に限られたため、大土地所有者が現れるようになった。このような状況の中、律令政府は天平15年(743年)にさらなる開墾促進策として墾田永年私財法を発布した。」(Wikipedia)
この解説を読むと、農地について、日本では古来、耕作者である農民による所有が認められてきたことがわかります。農地というのは常に耕作しないと荒れ地になってしまい、一旦荒れ地になると農地に戻すのには労力と年限がかかるということを古くから理解していたわけです。
土地所有については、所有者と国家との関係が関わっており、領土というのは国家主権の重要な要素ですから、未だ世界に領土をめぐる紛争が絶えません。私有地といえども、国家から完全に独立して、何でも自由にできるわけではないのですが、その原理をすべての人が共有しているかというと必ずしもそうではありません。いわゆる治外法権は領土内に存在する自国以外の者が所有している土地における法的な権利です。その典型例が大使館です。これは国家間の条約に基づく取り決めですから、私人には適用されないのですが、そこを誤解しているわけです。現在の中国では国土の私有は一切できないそうですが、日本の国土は国有地や自治体の公有地以外はすべて私有地であり、特別な事情がないかぎり、収公はありませんし、払い下げには制限があります。また農地は特別扱いで、一般の私有地のような売買は農地法によって制限されています。しかし近年、住宅地開発や農業の衰退によって、農地の荒廃がすすみ、古代は土地=農地であったのが、土地=私有地という概念に変わりました。背景には農地解放があり、一旦は自作農体制になったものの、次第に農地の荒廃化が進む結果となりました。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |