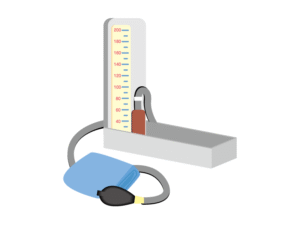政体書
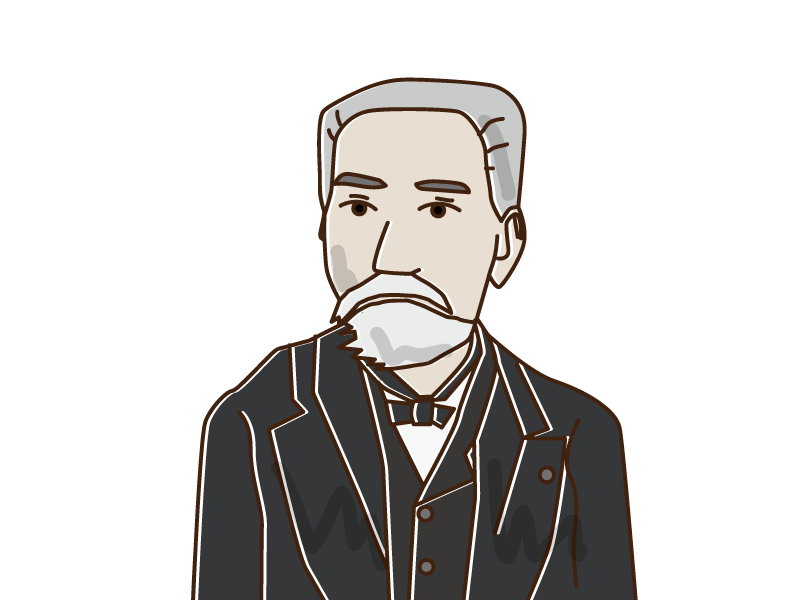
1868年6月11日(慶応4年閏4月21日)に明治政府は政体書を布告しました。これが真の意味の明治維新でしょう。政体書は明治初期の政治大綱で、統治機構について定めた太政官の布告です。副島種臣と福岡孝弟がアメリカ合衆国憲法および福沢諭吉の『西洋事情』等を参考に起草したものです。当時の最先端の政治思想ということになります。慶応3年12月9日の王政復古のクーデター、慶応4年1月3日 - 7日の鳥羽・伏見の戦い、4月11日の江戸開城と、次々に起こる政変などを経て、内戦としては、奥羽・北越地方では交戦が続いていたものの、関東地方以西をほぼ掌握した新政府が、それまでの臨時政府的な三職体制に代えて新たな官制を定めたものです。これで新政府が樹立されたということの公表ということになります。
政体書は冒頭に五箇条の御誓文を掲げてこれを政府の基本方針と位置づけ、国家権力を総括する中央政府として太政官を置き、2名の輔相(ほしょう)をその首班とする仕組みでした。太政官の権力を立法・行政・司法の三権に分け、それぞれを立法の議政官、行政の行政・神祇・会計・軍務・外国の5官、司法の刑法官の合計七官が掌る三権分立の体制とったのは、西洋の三権分立の思想が採り入れられたのですが、実際には議政官に議定・参与で構成する上局の実力者が行政各官の責任者を兼ねたり、刑法官が行政官の監督下にあったりして権力分立は不十分なものでした。理想と現実は必ずしも一致せず、権力機構はスタートからいびつな仕組みを内蔵していたと言えます。
地方行政は府藩県の三治を採用しました。完全な廃藩置県になる前に、こうした妥協的な府藩県三治制もあったわけです。府:は城代や京都所司代、奉行によって統治されていた地域、藩は明治維新以前から存在していた藩、県はそれ以外の地域と定められていて、府には府知事、県には知県事が任命され、藩は従来通り大名が支配しましたが、明治政府の力は藩には及びませんでした。まだ完全に中央集権にはなっていなかったのです。明治維新はクーデターという見方があるのは、この状態を指しています。クーデター直後の政府が弱体なのはよくあることです。
戊辰戦争終結後の政治状況の変化に伴う若干の変更の後、明治2年7月8日に新たに発布された職員令によって、太政官は二官六省体制に改められました。政体書の内容は、五箇条の御誓文を国家の基本方針とする(第1条)、太政官への権力集中と立法・行政・司法の三権分立(第2条)、立法官と行政官の兼職禁止(第3条)、各官の任期を4年とし、2年ごとに半数を改選する(第9条)、第一等官から第九等官の官等を定める(第13条)といったものでした。憲法として国の基本法令を定める以前の暫定的な法令であり、抽象的な内容になっているのは、西洋を意識した国民の意識改革を目指したものであることがわかります。聖徳太子の17条憲法と内容的にはよく似たものですが、まだ現実的な法制度には至らず、西洋の制度に近づけたい、という希望と、現実の混乱をまとめたい、という気持ちが混ざったものですが、明治維新の思想を知る上では興味深いものです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |