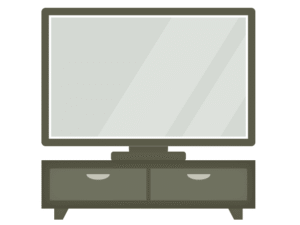八朔(8月1日)

八朔(はっさく)とは、旧暦の八月一日を指す日本の伝統的な日付であり、かつては五節句や節供と並ぶ重要な節目として、農村部から武家、町人社会に至るまで、さまざまな形で祝われてきました。現代では、その名称が柑橘類の「八朔(はっさく)」という果物にも受け継がれていますが、本来は、季節の移り変わりや人間関係の節目に感謝を表す日だったのです。語源の「朔」は「ついたち」、つまり月の初めの日を意味し、「八朔」は旧暦の八月一日を示します。
この時期は稲の穂が出始める「穂見の節目」にあたり、収穫の予兆を喜び、神々に祈りを捧げる日として、古代から重要視されてきました。農家にとってはこの日が、豊作を願う折り返し地点とも言え、秋の実りに向けた希望と覚悟が交差するタイミングでもありました。また、八朔は江戸時代の武士や町人のあいだでも特別な意味を持っていました。とくに徳川家康が征夷大将軍に任じられた日が慶長8年(1603年)の八朔であったことから、八朔は「徳川吉日」とされ、江戸城内では格式高い祝儀の儀式が行われるようになりました。この慣習はやがて民間にも広がり、商人たちは贔屓筋やお得意様に贈り物(八朔の祝儀)を届ける「お礼まわり」の日として八朔を利用するようになったのです。とりわけ、京都・祇園の花街ではこの風習が現在も色濃く残っています。
毎年8月1日には、舞妓や芸妓たちが正装で師匠やお茶屋、芸事の先生方に感謝の挨拶を行う「八朔の挨拶回り」が伝統として受け継がれています。これは芸能の世界における忠誠と礼節の象徴的な所作であり、日本の礼文化を体現する美しい儀式でもあります。こうした八朔の習慣は、単なる暦上の節目を超えて、「感謝と絆」を再確認する日としての意味を持ってきました。現代社会では日々の忙しさの中で、人との縁や感謝の気持ちを伝える機会が失われがちですが、八朔のような習慣が見直されることで、心の距離を縮めるきっかけになるかもしれません。
ちなみに、果物としての「八朔」は、広島県因島で発見され、昭和初期に全国的に栽培が広まりました。名前の由来は、「八月一日ごろに食べられる柑橘」という意味から来ており、まさに暦と自然の結びつきを感じさせる命名です。八朔は、古くは農の神に、武士は主君に、町人は商売相手に、芸妓は師匠に――それぞれの立場で感謝を形にする日でした。今ではその意識が薄れつつありますが、あらためて「ありがとう」の言葉を伝える機会として、八朔の心を現代に再生することは十分に意義があると言えるでしょう。私たちもこの8月1日には、日ごろの感謝の気持ちを言葉にしてみてはいかがでしょうか。八朔の精神は、令和の時代にも、きっと温かく受け入れられるはずです。
しかし、現実には真夏でもあり、すぐ近くの日に原爆の日が広島(8月6日)、長崎(8月9日)があるので、テレビはもっぱらそっちに関心を集めようとします。天気予報では八朔を紹介することはあっても、短い時間の中で昔の習慣まで紹介することはありません。そのせいか、現代人はハッサクは柑橘のことしか思い浮かばなくなっているのは、さみしいことです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||