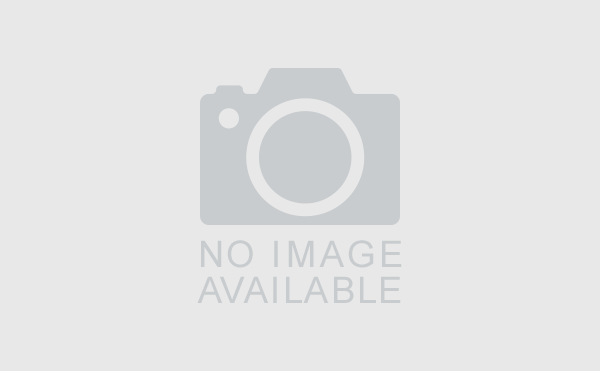世界初の油井が稼働
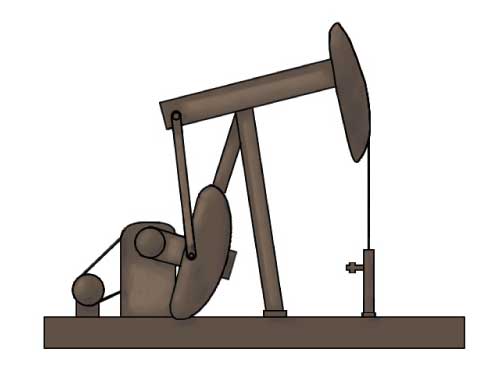
1859年8月27日、アメリカ・ペンシルベニア州タイタスビルという静かな田舎町にて、人類史上初めて、石油を意図的に地中から汲み上げる「油井(ゆせい)」が稼働しました。この出来事は、後の世界経済と文明の転換点となる産業の幕開けを告げたものでした。発明者の名はエドウィン・L・ドレーク。彼の挑戦と成功は、「石油時代」の扉を開いた歴史的な瞬間として今も語り継がれています。
19世紀半ば、それまで照明や潤滑油の主役だったのは、鯨の油でした。鯨油は高価で供給が限られており、工業化が進むアメリカ社会では、代替エネルギーの必要性が高まっていました。日本にペリーがやってきたのも、アメリカの捕鯨のためでした。当時、石油自体はすでに知られており、「地面からにじみ出る黒い液体」として民間療法や軟膏として利用されていました。だが、それを産業規模で採掘しようとする試みは存在しませんでした。地中から大量に石油を得るには、当時としては破天荒な発想が必要だったのです。
ドレークは元鉄道員で、石油業界とは無縁の人物でした。しかし、ニューヘイブンの実業家たちの出資により、ペンシルベニアでの石油採掘プロジェクトの責任者として選ばれます。石油採掘に関する経験も技術もない中、彼は試行錯誤を重ね、なんと鉄道で使われていたボーリング(掘削)技術を応用しました。資金は底をつき、人々の嘲笑を浴びながらも、彼は諦めませんでした。そして1859年8月27日、深さ21メートルでついに石油を噴出させることに成功します。この掘削装置にはポンプを備え、井戸から安定的に石油を汲み上げる仕組みが施されていました。これが後に「ドレーク井」と呼ばれる、世界初の商業用油井です。
この発見は一気に全米を駆け巡り、まさに「オイルラッシュ」が始まりました。カリフォルニアのゴールドラッシュさながら、タイタスビルには投資家、労働者、投機家が殺到し、一帯は一躍「石油バブル」の中心地となります。新たな井戸が次々と掘られ、石油の供給は急増。石油は灯油に精製され、ランプの燃料として普及しました。まさに家庭の夜を照らす「新たな光源」となり、エネルギー革命が現実のものとなったのです。さらに20世紀に入ると、内燃機関の発展により、石油は自動車、航空機、軍事などあらゆる分野の動力源として不可欠な存在となっていきました。
皮肉なことに、ドレーク自身はこの画期的な技術に特許を取得しておらず、利益を得ることはありませんでした。石油産業は彼の手を離れて巨大化し、スタンダード・オイルのような大企業が台頭していきます。晩年、ドレークは病と貧困に苦しみましたが、その功績が認められ、ペンシルベニア州政府から年金が支給されるようになりました。彼の名は、今では「ドレーク記念博物館」や「石油産業の父」として歴史に刻まれています。ドレーク井の成功は、世界各地での石油採掘のモデルとなり、ロシア、インドネシア、中東へと広がっていきました。特に20世紀後半からは、中東の石油資源が世界経済の鍵を握るようになり、エネルギー政策や国際政治にも大きな影響を与えています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |