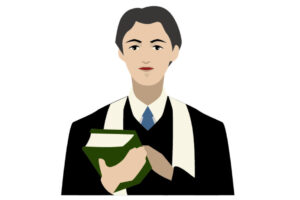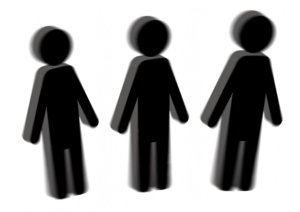一般意味論

一般意味論 General Semantics は Wikipedia の解説では「アルフレッド・コージブスキー(1879年 - 1950年)により1919年から1933年までの間に構築された教育的規範である。一般意味論は、言語学の意味論とは全く異なる」となっています。そしてコージブスキーについてのみ解説しています。しかし言語学の世界で一般意味論が有名になったのはS.I.ハヤカワによるところが大きいことが知られています。ハヤカワの『思考と行動における言語』(大久保忠利訳、原著 Language in Thought and Action, 1978)はベストセラーになり、一般にはこちらの方が有名です。ただこの著作は言語学者のような専門家の評判は芳しくないため、辞典類ではコージブスキーのみが紹介されるようになったと考えられます。歴史的な経緯はともなく、彼らの主張である「地図と現地の違い」という概念は今でも有効であると考える人が多いのです。言語技術を広告や政治や宗教による巧みに操作された意味論的歪曲に対する自衛手段が一般意味論のポイントで、現代のようにいろいろなメディアによる宣伝やプロパガンダが蔓延している時代には、その意味がより重要になったといえます。「言語などの表現方法によってどれだけの現実が破棄されているかということへの自覚である。一般意味論はこれを散発的に知識として理解するだけでは不十分としていて、「抽象過程への自覚」を常に持って反射的に実践することで完全な正気が達成されるとしている。」というのがポイントなのだが、これだけでは抽象的過ぎてわかりにくいです。そこでハヤカワは実際例で説明しています。原著を読むのが良いのですが、例が古いのと英語での例なので日本人にはわかりにくい面もあります。同書をうまく説明したサイトはほとんどないのですが、Hatena blog(https://huyukiitoichi.hatenadiary.jp/entry/20110510/1305037099)はうまく説明していると思います。「たとえば、「地震」という言葉は地震そのものではありません。言葉は物ではありません。言葉は物ではありません。同様に、記号も物ではありません。」ここが肝心なところで、両者を混同する人が実に多いのです。ドラマの役と役者との混同はしばしば見られます。「たとえば、僕たちは二つの世界に住んでいます。ひとつは自分が見て感じることが出来る小さな世界、もうひとつは僕達の感覚の前を通り過ぎていく出来事の流れです。たとえば僕はカナダに行ったことがありませんが、カナダという国のことを知っています。自分の身の回りで知り得る小さな世界についてを本書では外在的世界と呼び、言葉でしか知らない世界の事を言語世界と呼んでいます。僕達の周りのほとんどの世界は他人の報告の報告の報告を聞いて知っている言語世界で成り立っています。この関係は、地図とそれが代表する現地の関係に似ているといえるでしょう。地図はたしかに存在していて、現実を反映させたものではあるけれども現実そのものではない。例え直せば、言葉が地図で、実際の外在的世界が現地です。もし現実に即した、正しい地図(言葉)を持っていればその人は予想外の事態にもきっと、正しく行動できるでしょう。」
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||