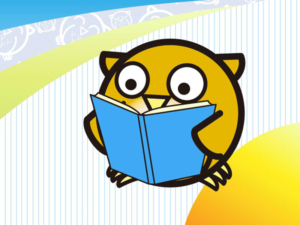言語技能測定技術と言語教育理論⑰ Useful Signs

手話技能検定協会のホームページに「Useful Signs検定」というコーナーがあります。(https://www.shuwaken.org/UStest/index.html)
解説のPDFには「Useful Signs 検定は、テキストにより自分で学習していただきその結果を測るところが違います。従って合否判定はせず、点数だけをお知らせします。」「受験は有料ですからお金がかかりますが、学習だけなら無料です。これは実際にUseful Signs~つかえる手話を広めたいという考えだからです。」と書いてあります。PDFなのでわざわざ開いてみる人も少なく、世間には広がっていないようです。しかしこのサービスには手話技能検定協会の思想が反映されていますから、ご紹介させてください。「Useful Signs ~つかえる手話の考え方は、将来の自分にも役立つことを前提としています。なぜなら、若い人が手話を習うことで、中途失聴者・難聴者・高齢者を支援し、さらにその人自身が高齢化などにより難聴になり、あるいは高齢化した時、今度は支援を受けることができるようになるからです。いわば「助け合い手話」です。世代間相互扶助という考えです。若いうちに手話を学習し支援することで、手話の習熟度が高ければ高いほど、自分が支援される側になった時のメリットも大きいのです。」ここでいう「助け合い手話」という考え方はまだ普及していませんが、手話学習の意義を考える上で重要です。聾者とコミュニケーションしたい、聾者の役に立ちたい、という学習動機はすばらしいものですが、自分にも役立つということも知っておきたいものです。
「手話は音声言語の影響を常に強く受けます。手話が発生した時点から、聴者の言語と混じり合って作られてきました。手話が発生した段階では、ジェスチャーに近いもので、周囲の聴者も直感的にわかるような仕草でした。現在の手話にもその名残が多く見られます。現在の手話は、語彙(単語)としてかなり発達しており、学習しないと直感的には理解できないほどですが、手話通訳制度が生まれる前の手話は語彙が少なく、ジェスチャー的な表現の割合が非常に多かったのです。そのため、昔は手話が言語ではないと考えられ、手真似(てまね)と呼ばれていました。現在の手話は、手話通訳の必要もあって、日本語からの借用が急増し、日本語とのハイブリッド化が急激に進んでいます。この高度に発達した手話は、難聴者や高齢者など、聴覚障害になってから日の浅い人には学習が困難です。そこでUseful Signs 検定では中途失聴者・難聴者・高齢者の方々にもできるだけ直感的に理解できそうな語彙を選定しました。」この解説では、手話の多くがジェスチャー起源であること、そして日本文化を共有する聴者も同じ仕草をすることが多いので、「わかりやすい」「使いやすい」のです。Usefulとは「役立つ」という意味ですが、他人に対してだけでなく、自分にも役立つのです。そしてなにより、直感的に使えるジェスチャーに近い手話語彙だけが選別されています。検定試験を受けるのは任意ですし有料ですが、学習だけなら無料です。どんな手話があるのか、本格的な手話学習を始める前に覗いてみてはいかがでしょう。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |