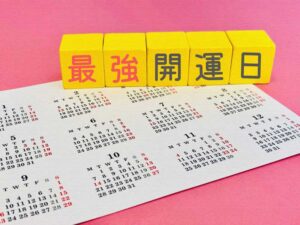3.11

3月11日近くなると、テレビはやたら防災をいい始めます。それは悪いことではないのですが、「災害はいつやってくるかわからない」のですから、本当にその意味をわかっているなら、みんながまだ覚えているこの時期ではなく、まったく関係のない時期にこそ、防災の案内や警告をだすべきでしょう。3月の東日本大震災だけでなく、1月の阪神淡路大震災など、大都市が震災にあったというのは、世界的にも珍しい出来事といえます。大都市だけでなく、能登も熊本も最近の出来事です。地震のニュースがよく出ますが、震度程度ではあまり驚かなくなっているほど、日本中に地震があります。世界には地震がよく起きる国は、日本以外にもありますが、大半の国では、たまに大地震が起こることはあっても、普段、それほど地震が起こることはなく、「地面が揺れる」というのは驚愕なのです。日本にやってきた外国人は、地震があると、その恐怖はものすごいもので、周囲の日本人が平然としているのを見て、非常に驚きます。また、これまでの震災の体験から、コンロやストーブに耐震装置がついていること、家も耐震化が進んでいること、津波対策としての避難訓練などを知ると、非常に納得すると同時に感心します。一方で、日本にいる外国人は、防災情報などにアクセスしにくい、とか、避難訓練に参加しない、といった傾向が強いのも、体験がないことが影響してそうです。インバウンドでやってくる外国人が遭難するニュースが時々ありますが、インバウンド客のほとんどは、天災への関心は薄く、リスク回避の安全策をとる人が少ないことが影響しているかもしれません。諸外国では、天災による被災リスクよりも、治安の悪さによる被害の方が頻繁なためだと思われます。リスク意識の違いが大きいわけです。日本人の場合、もし旅先で震災に遭遇しても、それなりの対処ができそうですが、外国人旅行客は慌てふためくだけで、パニックになるだけなのは、言語の問題ではなく、その土地特有の自然と行動という文化的背景の違いによります。また被災すると、避難先として学校や公的施設が提供され、時にはホテルや旅館が提供されることも驚きのようです。そして、おにぎりやインスタント食品、パンなどに加えて、普段備蓄されている食品類が提供されます。こうした食品に文化が反映されるのは当然のことなのですが、その国ごとに食文化が異なるため、外国人には驚きのようです。いわゆる「炊き出し」が提供されることは、ほぼ同じでも、炊き出しの中身はかなり違います。その是非は問うべきものではなく、わざわざ外国人向けに準備するものでもありません。それは外国人と一括りにできるものではなく、国ごとに違うためです。災害時は、まず生存の確保ですから、郷に入りては郷に従え、というルールになります。逆にいえば、日本人が外国旅行中に、もし被災した場合、その被災内容は日本とは異なり、対応も異なる、ということでもあります。そして、それはいつ起こるか予想もできません。「自助、共助、公助」が重要と言われますが、海外では「自助」がまず第一ということを覚えておくべきです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||