夕餉前
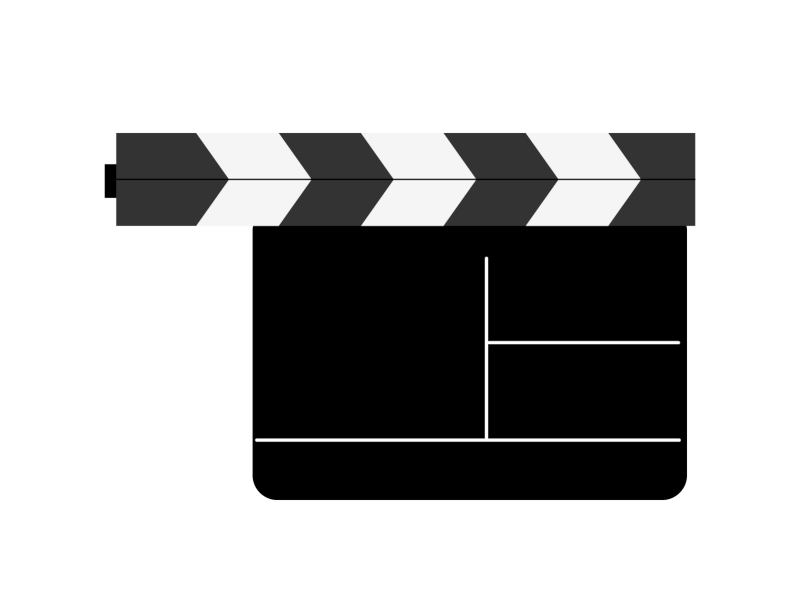
今年はNHKドラマが好評のようです。ドラマ制作にはセットやロケなど費用がかかるため、スポンサーが少なくなった民放にはむずかしくなってきたのかもしれません。
4月13日は1940年に日本放送協会(NHK)のテレビ技術実験放送において制作された、日本初のテレビドラマ「夕餉前」が放送された日です。伊馬鵜平(のちの伊馬春部)脚本による12分ほどのホームドラマで、適齢期の娘の縁談を中心とした内容だそうです。(wikipedia)4月13日(2回)、14日、20日に東京市世田谷区のNHK放送技術研究所のスタジオから生放送されたそうです。放送はNHK東京放送会館、愛宕山の旧演奏所(現在のNHK放送博物館)にある「常設テレビ観覧所」、百貨店・日本橋三越で開催されていた「電波展」内の受像機の3か所に送信されたとのことです。20日にはこの3か所に加え、当時開催されていた「輝く技術博覧会」の会場である、上野の産業会館に設置された受像機にも送られ、一般に公開されたそうです。まだまだ特別な技術だったのですが、戦争も近い時期ですから、現代から見ると驚きです。
あらすじと演出:舞台となっているのは、父をすでに亡くし、母と息子と娘の3人で暮らしている母子家庭です。娘が縁談を経て嫁ぐこととなったある日、家族3人で食卓を囲んで、夕食の前にこれまでの生活を振り返る、というものです。実際に登場する人物はこの3人のみですが、途中で豆腐屋の声も入という効果も入れられています。作品の母子家庭という設定は、のちの単身家庭ドラマの原型となったとされています。作中で息子が放送当日の新聞を見て、トップ記事の見出しを読む場面があり、これは、録画手段がなかった当時のテレビの生放送が持つ共時性・同時性を表した演出でした。また、当初の脚本では家族ですき焼きを囲む場面が設定されていました。このような場面を作品に盛り込んだ理由は、テレビドラマが聴衆に対して音声と画像を届けられる特性を生かし、肉が焼けるジュウジュウなんて音も入り、おいしそうな湯気の立つ鍋、楽しそうな家族の表情を撮影することで「テーブルを囲んで、家族が食事をするなごやかなひととき」を演出できるという考えからでした。この構想は技術的な制約から断念せざるを得なくなったものの、食事シーンはのちにホームドラマの定番となったとされています。
キャストは母:原泉子、篤(兄):野々村潔、貴美子(妹):関志保子でした。原泉子(はら せんこ)の本名は中野政野で、夫はプロレタリア作家・文学者の中野重治です。野々村潔は女優の岩下志麻の父で、妻は元女優の山岸美代子。元前進座の河原崎しづ江は義理の妹という芸能一家です。スタッフは、作:伊馬鵜平、演出:坂本朝一、川口劉二で、坂本朝一は後にNHK会長になりました。
1930年6月1日に設立されたNHK放送技術研究所は1937年にテレビ実験を成功させた高柳健次郎を部長に招聘し、1939年5月13日にテレビジョン放送の実験放送を開始しました。NHK側の実験担当に任命されたのは、のちに毎日放送取締役となる川口劉二、坂本朝一など、当時30歳前であった若手を中心としたスタッフでした。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


