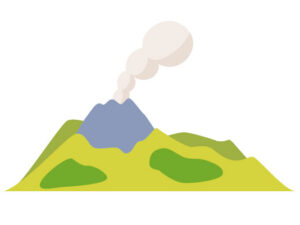昭和の日

4月29日は「昭和の日」という祝日です。昭和生まれにとっては、不思議な気分がします。最近は「昭和レトロ」というのがブームになっていますが、令和の若者にとって、昭和は「新しい」ということになるのだそうです。確かに今は令和時代で、その前が平成、昭和はその前なので、昭和時代に、大正や明治がレトロだったのと同じ感覚であることはわかります。こうした昔を懐かしむのではなく、新しいコンセプトと考える風潮の根底には、現在に対して、失望感というか、悲観的な感覚があって、その裏返しのような気がします。もし現在がイケイケの楽しい時代であれば、レトロには関心が向かないものです。本稿の著者もレトロ嗜好ですが、対象は江戸時代であり、さらに古い時代への関心が強いです。幸い、この国には古いものを大切にする伝統があり、その前の戦国時代、室町時代、鎌倉時代、平安時代、奈良時代、飛鳥時代の遺跡も残っていて、歴史の時間に学んだ事象の現地が今も残っています。むろん、長年の経過によって、周囲の環境は変わってしまっていますが、焼失した建物は再現されたり、記録を元に復興されるなどの努力が続いていて、歴史が視覚化され、体験できるようになっています。世界には、多くの遺跡がありますが、ほとんどは再建されることはなく、崩れたままの状態で、痕跡すらよくわからない状態になっていることが多いのです。あるがままに、崩れていく姿も歴史である、という価値観と、再現して今の人にも理解させようという価値観の違いが、結果に表れているといえます。それは歴史観の違いともいえます。「歴史は過ぎ去ったもの」と考えるか、「歴史は今も続いている」と考えるか、という違いです。この考えは、人の命は一代限り、死んだらおしまい、という死生観と、人の命は代々受け継がれている、という死生観の違いにも繋がっていきます。日本人は先祖という概念は受け入れやすいものですが、とくにアメリカのような移民国家では、ルーツという概念になり、それも複雑に絡み合った人種問題と関係しています。アメリカ人は日本で住むようになって、周囲の人々に祖先があって、歴史に出てくるような人の末裔が、ごろごろいることに非常に驚きます。欧米では、そういう祖先をもつのは貴族や名家の出身しかありえないのですが、日本には庶民にも、そういう人々がたくさんいることに驚くのです。店も百年以上続いていることがそれほど珍しいことではないですが、欧米人からすると驚異的です。現代中国人が中国五千年の歴史を自慢したがりますが、それは土地だけのことで、家系は皆無でしょう。それは支配者が頻繁に変わり、民族も入れ替わっているからです。一般に歴史が短い人ほど、歴史を自慢したがるのは、劣等感の裏返しかもしれません。人生においても、子供は早く大人になりたがり、年を取るにつれ、年を取りたくなくなり、若い時代を懐かしがるようになります。若いうちは前向き、年を取ると後向きになるのですが、それは歴史が長くなるから当然のことです。その歴史から学ぶことが、それ以降の人生を決めるといえます。昭和から何を学ぶのでしょう。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |