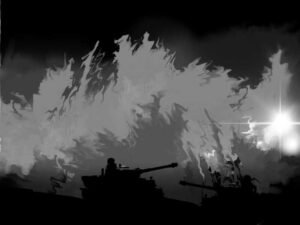開国の扉を開いた「ハリス条約」─1858年7月29日の意味

1858年7月29日、日本とアメリカ合衆国との間で「日米修好通商条約」、通称「ハリス条約」が締結されました。この条約は、江戸幕府による鎖国政策が終わりを告げ、近代日本が国際社会へと歩み出す大きな転換点となりました。表面的には「通商」を目的とする条約でしたが、その内実には当時の国際情勢、幕府の政権維持、攘夷運動の台頭など、複雑な力学が交錯していました。日本が本格的に開国を迫られる契機となったのは、1853年のペリー提督率いるアメリカ艦隊、いわゆる「黒船来航」でした。これを受けて翌1854年には「日米和親条約」が締結され、下田・函館の開港とアメリカへの最恵国待遇が認められました。しかし、これではまだ本格的な貿易や外交の枠組みは整っていませんでした。そこで来日したのが、アメリカの初代駐日総領事タウンゼント・ハリスです。彼は和親条約を土台に、より踏み込んだ「修好通商条約」の締結を目指して交渉を始めました。条約締結までには約3年もの歳月を要し、その過程には幕府内の意見対立や将軍継嗣問題なども絡んでいました。ハリスが示した条約案は、日本にとって非常に不利な「不平等条約」でした。関税自主権が認められず、外国人に対しては領事裁判権(治外法権)を与えるという内容です。幕府内ではこれに強く反発する声も多く、調印には大きな政治的リスクが伴いました。
この局面を打開したのが大老・井伊直弼です。彼は天皇の勅許を得ないまま、1858年7月29日、独断で日米修好通商条約に調印しました。この決断は「安政の大獄」と呼ばれる弾圧へとつながり、尊王攘夷派や反条約派の弾圧が強行されることになります。条約では、神奈川(横浜)、長崎、新潟、兵庫(神戸)の開港が定められ、下田は閉鎖されることになりました。また、日本はアメリカの領事裁判権を認め、アメリカに関税の決定権を与えることになりました。これにより、日本は自国の関税政策を自由に運用できなくなり、安価な外国製品の流入によって国内産業は大きな打撃を受けました。さらに、金銀の交換比率の不均衡を突かれ、大量の金が国外に流出する「金流出問題」も深刻化しました。経済の混乱と物価の高騰は庶民の生活を圧迫し、幕府への不信を高めていくことになります。
とはいえ、ハリス条約の締結は日本が鎖国から脱し、近代化と国際化への第一歩を踏み出す契機でもありました。条約締結後、日本はオランダ、イギリス、フランス、ロシアとも同様の不平等条約を結ぶことになり、いわゆる「安政の五カ国条約」が成立します。これにより、日本は否応なく世界の一員としての立場を求められるようになりました。その後、明治維新を経て日本政府は条約改正交渉に着手し、長い年月をかけて不平等条約の是正を果たしていくことになります。ハリス条約調印は、日本にとって苦渋の選択でありながらも、近代国家への胎動を感じさせる歴史的出来事でした。一方で、この条約によって引き起こされた内外の混乱や政治的対立は、幕末の不安定な政局をさらに揺さぶる結果となりました。日本の近代化と国際化の原点であり、痛みを伴いながらも新たな時代への扉を開いたといえます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |