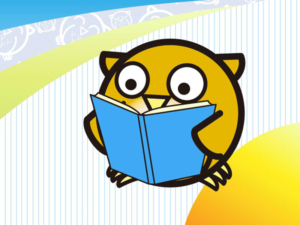言語技能測定技術と言語教育理論⑱ 表現試験1
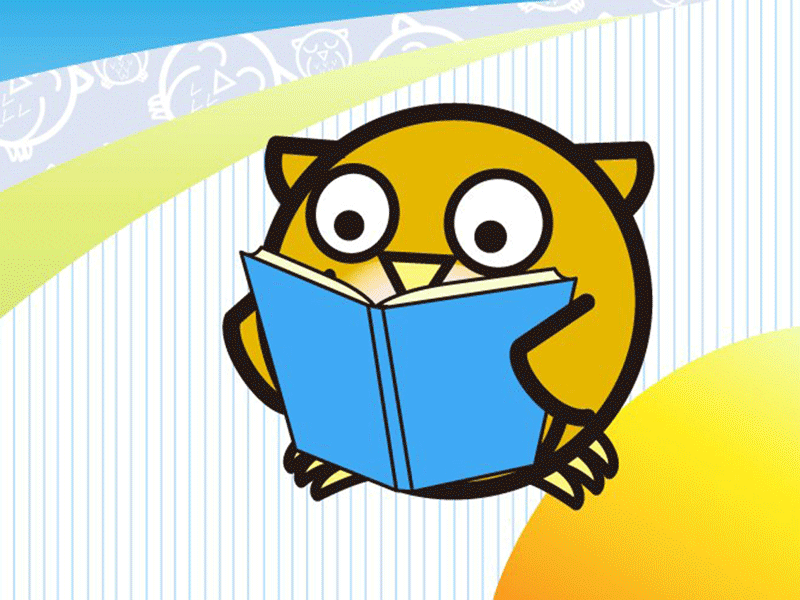
手話技能検定試験では、3級までは、「ビデオを見て、選択肢で回答を選ぶ」という「理解度」の試験です。これは、前述の理解語彙と使用語彙の原理に依っています。学習初期段階では、理解語彙と使用語彙の範囲はほぼ同じなのですが、学習が進むにつれ、使用語彙の範囲をはるかに超えた理解語彙をもつようになります。つまり、学習者の理解度を測定するには、理解語彙をテストすればよいのは中級程度まで、ということになります。手話技能検定試験では「3級までを中級」と考えている、ということになります。それ以上の「上級」を測定するには、使用語彙を調べなければなりません。使用語彙は教育的に範囲を制限することはなく、学習者によって個人差が大きいものです。専門用語で「社会変数」といいますが、性別、年齢、職業、地域など、その人の社会的背景や、状況や場面などによっても、使用が変わります。たとえば、日本語の敬語がその典型例です。敬語表現や丁寧表現は、人によって異なるだけでなく、仕事先や立場によって表現が変わります。それも言語学習なのですが、普通は社会訓練と考えられています。外国人にとって、敬語や丁寧語を使いこなす「上級者」になるには相当苦労があります。日本語の一人称を表す名詞は「私、オレ、僕、オイラ、アタシ、アタイ、拙者、愚僧…」など多くの表現がありますが、これらは社会変数を意味しています。欧米の言語であれば、一人称代名詞「I」など1つで済みますから、外国人が苦労するのもわかります。逆に日本人からすると、「外国語には敬語がない」と誤解することになりがちです。実際には、どの言語にも敬語のような用法はありますから、上級者になるには、必要な学習過程です。しかし、日本の英語教育では、英語の敬語や丁寧表現を教えないため、初級~中級で終わっています。「実用」をどこまでにするかですが、挨拶程度の簡単な会話であれば、それほど高いレベルは必要がないかもしれません。しかし社会的な場面であれば、上級であることが求められます。そして、上級にも段階があります。「英語がペラペラ」とか「ネイティブ並み」とよくいいますが、本当にぺらぺらな薄いものでよいのか、またネイティブにもいろいろな人がいます。中級以上になれば、どこを目標にするのか、よく考えなくてはなりません。手話技能検定試験では、検定試験という性質上、2級と1級に分けています。そのレベルの基準は、2級が地域における手話通訳者程度、1級が手話通訳士程度、と設定しています。通訳という概念を導入しているため、どちらの試験にも「課題文」があり、「翻訳力」を測定しています。2級までは「試験範囲語彙」が公開されているので、課題文において、2級語彙が習得されているか、が判定基準となります。2級語彙を指文字や空書で表現すれば、減点されます。表現試験には課題文翻訳の他に、コミュニケーションに必要な表現力が測定されます。「上級者」であることが前提なので、初級者のような「たどたどしい」会話表現では合格しません。しかもその場の対話ではなく、練習して録画するしくみになっていますから、基準は高くなります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |