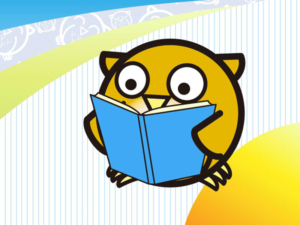言語技能測定技術と言語教育理論⑲ 表現試験2
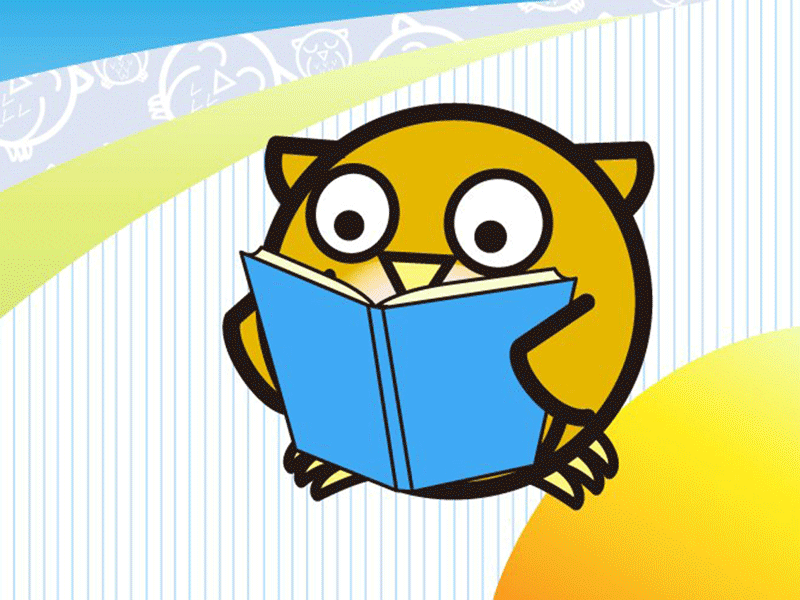
1級は手話技能検定試験の最上級ですから、課題文、自由文ともかなりのレベルが要求されます。試験制度設立当初は、対話能力を重視していましたから、「手話による討論」という試験方法を採用していました。しかし、あまりに受験者が少なく、合格者も少なかったため、試験方法を変更しました。また、討論形式は苦手な日本人が多いのと、遠慮がちな人や、反論を述べることに抵抗感のある人も多い、という日本文化もあり、成功しませんでした。また審査方法も、司会者がすべて判定するのではなく、テレビの討論と同じく、すべての人の発言を複数のカメラで録画し、後日、複数の審査員がそれらをすべてチェックしなければならない、という負担も大きく、費用も時間も掛かるため、実施が困難でした。そのため、自由度はかなり下がりますが、討論形式ではなく、手話スピーチのような自由作文形式に変更しました。この形式であれば、一部を先生に指導してもらうとか、友達に相談する、辞書や書籍を調べる、などの補助手段が可能になり、表現技術は実力より高くなります。しかし「その過程も学習」と当協会では考えています。検定試験は学習結果の測定であり、更なる学習への動機となることを期待しています。1級に合格したから目標達成、ではなく、さらに学習を続けることで、プロとしての道を目指す、ためのステップである、と考えています。また現場を考えると、理解語彙や使用語彙は無限ですから、試験範囲を限定していません。当然、「まだ習っていない語」が出る可能性もあります。それを「推測」する能力も理解力の一部です。また、これまで「使ったことのない」語も出てくることがあります。その時には「なんとか相手にわかってもらえる」ような新規表現を工夫する能力も必要です。こうした能力の測定を前提として、課題文には、まだ普及していない「新しい手話」や最近の流行語、日本語の外来語なども登場します。事前にダウンロードして検証できますから、実際の手話通訳場面よりはやさしい、といえます。最近の手話通訳現場では、講演者に事前に原稿を提出してもらうことも一般的になっていますから、そうした実情も反映しています。自由作文では、自由な表現を駆使して、言いたいことを相手に伝える工夫が問われます。ただメッセージを伝えるだけでなく、非言語情報を活用して、わかりやすく伝える工夫が大切です。それは表情や動きで感情的な情報を伝えるだけでなく、言語情報と非言語情報の中間にある、パラ言語情報つまりリズムや強弱、長短、高低、間といった情報をうまく組み込むことが必要です。ネイティブの場合は、こうしたパラ言語情報を自然に習得するのですが、言語学習者にはなかなかむずかしい領域です。語学では、パラ言語情報の習得に力を入れていて、リズム学習などが盛んに行われています。ネイティブとの接触が多いと、「自然に」学習できる機会も多いのですが、それでは時間もかかりますし、体系的な学習機会が必要です。一番簡単な技法は「ものまね」です。しかし、実際にはネイティブと同じようにはなかなかできないのが実情です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |