足利義尚(よしひさ)
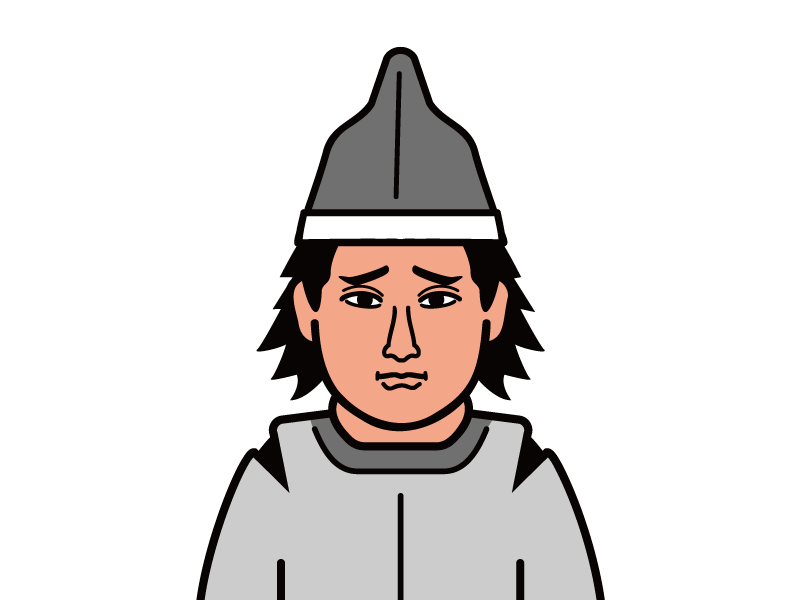
延徳元年(1489)3月26日(旧暦)室町幕府9代将軍 足利義尚が亡くなりました。応仁の乱では叔父の足利義視と将軍職をめぐる対立候補として擁立されました。乱後は衰退した幕府権力を回復すべく、六角征伐などの積極的な幕政改革を行なったのですが、在陣していた近江国の陣中にて病死しました。美しい顔立ちから「緑髪将軍」と称されました。
古記録によると「御容顔いとも美しく、すきのない玉の御姿」とあるそうです。義尚は一条兼良から政道や和歌などを学ぶなど、文化人としての評価は高いです。イケメンの将軍なので、漫画のネタになっていそうな気がするのですが、この頃の時代を描いた漫画に「新九郎、奔る! 」(ゆうきまさみ)があります。主人公は義尚ではなく、後に北条早雲となる伊勢新九郎です。
義尚は和歌に熱心で、文明10年(1478年)頃から盛んに歌会を主催しました。文明15年(1483年)10月には『新百人一首』を撰定し、さらに姉小路基綱や三条西実隆、飛鳥井雅親、宗祇などの歌人を結集して和歌『撰藻鈔』の編纂を試みましたが、義尚の陣没により未完に終わりました。
寛正6年(1465年)11月23日、8代将軍・足利義政と正室・日野富子の次男として生まれました。義尚が誕生する4か月前の7月には側室の茶阿局が男子(等賢同山)を出産しているのですが、庶子である彼を後継者にするつもりがなかった義政は翌年4月には出家させるために天龍寺香厳院へ送っています。つまり、初めから義尚が将来の将軍家の後継者となることが前提となっていたわけです。長らく実子のなかった義政は弟の義視を養子にしていたのですが、義尚が誕生すると将軍後継問題が発生しました。義政は弟の義視を中継ぎとして就任させてから、その上で義尚を将軍にするつもりでしたが、義尚の養育係であった政所執事・伊勢貞親は義視の将軍就任に反対でした。この時点で争いになっていたわけです。
文正元年(1466年)9月、貞親は義視に謀反の疑いありと義政に讒言し、義視の排除を図ったのですが、義視が細川勝元の邸宅に駆け込み救援を求めると、勝元は山名宗全と結託して義政に抗議し、これにより貞親は失脚し京を去りました(文正の政変)。これで義視の将軍就任も間近と思われたのですが、山名宗全は幕政を牛耳ることを目論み、畠山氏の家督をめぐって畠山政長と争っていた畠山義就を味方に引き入れ、義就に上洛を促します。義就と宗全は御霊合戦で政長を破ったものの、政長に肩入れしていた勝元が反撃を開始し、応仁元年(1467年)、「応仁の乱」が勃発しました。
勝元の要請に応じ、義政は東軍に将軍旗を与え、西軍を賊軍としました。これにより、東軍は正当性の面で優位に立ったのですが、大内政弘が入京すると西軍は形勢を盛り返し、戦局は膠着状態となりました。応仁2年(1468年)、義政が、かつて義視を陥れようとした貞親を政務に復帰させると、これに反発した義視は西軍へと出奔した。これにより、義視が将軍に就任することはなくなりました。応仁の乱後、下克上の風潮によって幕府の権威は衰退しました。ちなみに京都人が「さきのいくさ」と言う時は応仁の乱のことだそうです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


