島原大変肥後迷惑
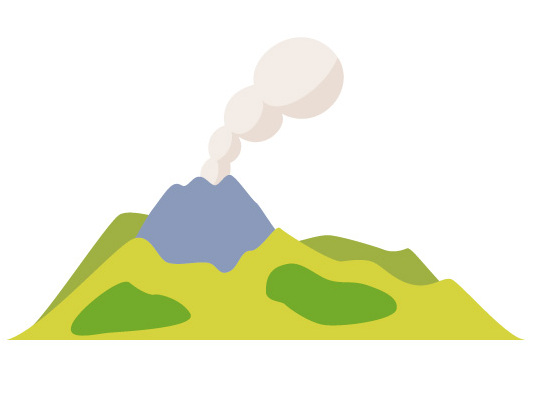
島原大変肥後迷惑(しまばらたいへんひごめいわく)とは、江戸時代の1792年5月21日(寛政4年4月1日(旧暦))に肥前国島原(現在の長崎県)で発生した雲仙岳の火山性地震およびその後の眉山の山体崩壊(島原大変)と、それに起因する津波が島原や対岸の肥後国(現在の熊本県)を襲ったこと(肥後迷惑)による災害である。(wikipedia)
「犠牲者は約1万5000人に達し、日本史上最大規模の火山災害となった。新月の夜かつ大潮であったことで大きな被害になったとされる。シミュレーションによれば、山体崩壊開始から終了までは 180秒程度と想定された。寛政4年3月1日から1週間ほど地震が群発し、普賢岳から火が噴き、吹き上げられた石は雨のごとく地面に降り注ぎ、また前に聳える眉岳・天狗岳(708メートル)に落石し、地割れが各所で起こった。その後、地震は島原の近くに震源を移し、有感地震が続いた。4月21日からは、島原近辺での地震活動が活発になった。山体崩壊で大量の土砂が有明海になだれ込んできた衝撃で、10メートル以上の高さの津波が発生した。津波の第1波は約20分で有明海を横断して対岸の肥後天草に到達した。大量の土砂は海岸線を870メートルも沖に進ませ、島原側が高さ6-9メートル、肥後側が高さ4-5メートルの津波であったという。肥後の海岸で反射した返し波は島原を再び襲った。津波による死者は島原で約10,000人、対岸の熊本で5,000人を数えると言われている。肥後側の津波の遡上高は熊本市の河内、塩屋、近津付近で15-20メートルに達し、三角町大田尾で最高の22.5メートルに達した。島原側は布津大崎鼻で57メートルを超えたとの記録がある。島原大変肥後迷惑は有史以来日本最大の火山災害であり、島原地方には今も多くの絵図や古記録が残っている。この時に有明海に流れ込んだ岩塊は、島原市街前面の浅海に岩礁群として残っており、九十九島(つくもじま)と呼ばれている。これは地形学的に言うと「流れ山」と呼ばれる地形である。同じ長崎県の佐世保市から平戸市にかけて九十九島(くじゅうくしま)と呼ばれる群島があるが、島原市の九十九島とは別のものである。」(引用同上)
同じような自然現象が1991年6月3日の火砕流です。報道関係者が犠牲となったことで報道機関は大騒ぎでした。長崎・島原市北上木場地区。 その「定点」と呼ばれる一帯の保存、整備構想をしているそうです。 消防団や警察官の犠牲は「マスコミの行き過ぎた取材活動によるもの」とされ、二次被害ともいえるものです。そのため、マスコミには冷ややかな視線が注がれてきました。 被害者に無遠慮なインタビューをしたり、被災地で宿泊や食事をしてボランティア活動の邪魔をしたりと、自分勝手な行動が多大な迷惑をかける姿勢は今もそれほど変わってはいません。しかし、2021年に被災から30年を迎えるのを期に、地元・安中地区から、災害報道を考え続ける場所になりました。最近は視聴者の動画の方が、迫力があるため、もっぱらネット頼りの取材も増えてきました。テレビは一過性の報道でも、ネットには永久に残るため、資料映像としての価値はむしろネット情報にあるといわています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


