お初天神
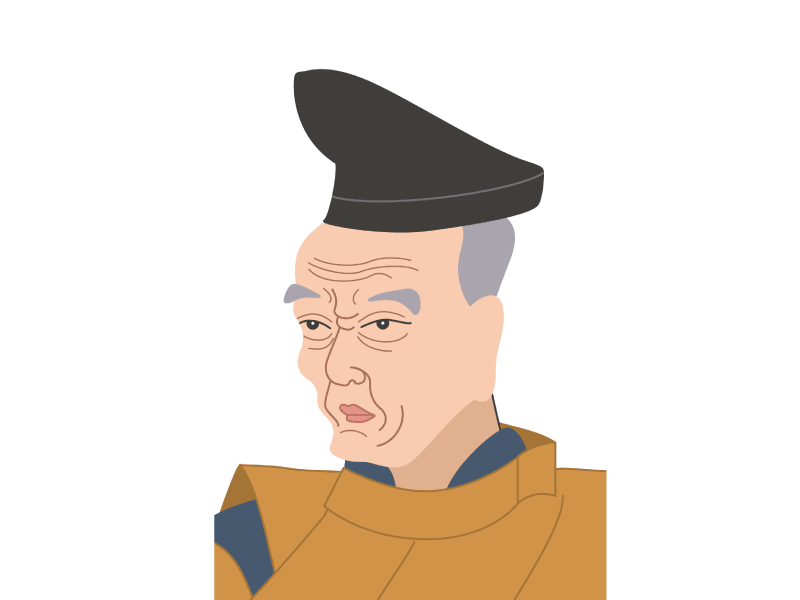
元禄16年(1703)に起きた悲恋の事件が大阪梅田のお初天神の由来です。堂島新地天満屋の遊女「お初」と、内本町平野屋の手代「徳兵衛」が、天神の森(現在の露天神社の裏手)で心中を遂げた事件です。この事件を題材に、劇作家の近松門左衛門が人形浄瑠璃「曽根崎心中」を制作し、広く民衆の涙を誘いました。この作品のヒロイン「お初」の名前から「お初天神」と呼ばれるようになり、現在でも恋愛成就を願う参拝者が訪れる「恋人の聖地」として親しまれています。ただ現在は浄瑠璃の方は参拝者の多くもよくは知らない様子です。最後は心中するという悲恋ですから、恋愛成就といえるか、どうか、という疑問はなさそうです。
露天神社の歴史は1300年以上前に遡り、かつて大阪湾に浮かぶ小島「曾根崎洲」に祀られていた「住吉須牟地曽根ノ神」が起源とされています。その後、菅原道真公が大宰府へ左遷される途中で詠んだ歌「露と散る涙に袖は朽ちにけり 都のことを思い出ずれば」に由来して「露天神社」と名付けられたとも伝えられています。
「曽根崎心中」は実際に起きた心中事件を題材にした近松門左衛門の人形浄瑠璃作品です。この物語は、恋仲であった醤油商の手代・徳兵衛と遊女・お初が、社会的な圧力や裏切りに直面し、最終的に曽根崎の森で心中するまでを描いています。徳兵衛は叔父から結婚を強要されるも、お初への愛を理由に拒否します。しかし、友人の九平次に結納金を貸したことで裏切られ、詐欺師呼ばわりされてしまいます。絶望した徳兵衛は、お初とともに死を選び、二人は曽根崎の森で命を絶ちます。この物語は、二人の純愛と悲劇を描き、当時の社会に大きな衝撃を与えました。ドキュメンタリーではないので、近松による創作部分もありますが、戯作が売れるとそれが事実のような誤解も広がります。現在の「あんぱん」でもヒロインとモデルの漫画家が幼馴染という設定ですが、これは創作です。しかし今後はそれが事実かのように広がるのでしょうね。
曽根崎という地名は今も残っていて、リアリティもあります。「曽根崎心中」は近松門左衛門が「世話物」というジャンルを確立した代表作であり、後に歌舞伎化されるなど、広く愛される演目となりました。また、心中事件が増加する社会的影響を受け、幕府は心中物の上演を禁止するに至りました。近松門左衛門の世話物には、以下のような代表的な作品があります。『冥途の飛脚』(1711);商家の手代・忠兵衛が遊女・梅川を身請けするために店のお金を流用し、二人で逃亡を図る物語です。義理と人情の葛藤が描かれています。『心中天網島』(1720):紙屋の治兵衛と遊女・小春の恋愛を中心に、治兵衛の妻や親族との関係を描いた作品です。心中事件を題材にした傑作として知られています。『女殺油地獄』(1721):放蕩息子の与兵衛が借金返済のために油屋の妻を殺害する事件を描いた作品で、リアルな人間描写が特徴です。これらの人形浄瑠璃が人気を博したため、現在では歌舞伎で演じられることもあります。映画になることもあります。そのたびに脚色が入るので、楽しんだ人々の間で事実の食い違いがでることもしばしばです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |


