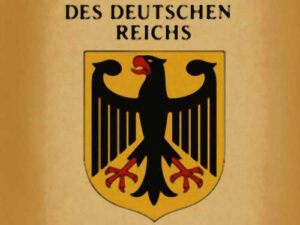パーソナルコンピューター革命の幕開け─IBM 5150の登場

1981年8月12日、アメリカのコンピューター企業IBMが、初のパーソナルコンピューター「IBM 5150」を発表しました。この出来事は、世界のIT史において非常に重要な転換点であり、現代社会の情報化に大きな影響を与えました。当時のIBMは、大型コンピューター(メインフレーム)の分野では圧倒的なシェアを誇っていましたが、個人向けコンピューター市場ではAppleやCommodore、Tandyといった先行メーカーがすでに製品を出していました。IBMは、こうした企業に遅れをとっていましたが、いよいよ本格参入を果たしたのが「IBM 5150」だったのです。
「IBM 5150」は、今日の私たちが使っているパソコンの原型ともいえる製品でした。その特徴のひとつが、「オープンアーキテクチャ」という設計思想です。これは、IBM自身がすべての部品やソフトウェアを自社開発するのではなく、外部企業の技術や部品を積極的に取り入れるという方針でした。たとえば、CPU(中央処理装置)にはインテル社の「8088」を採用し、OS(基本ソフト)には当時まだ無名だったマイクロソフト社の「MS-DOS」が使われました。この選択が、のちにIT業界全体の構造を大きく変えることになります。
特に注目されたのは、マイクロソフトとの提携です。マイクロソフトは、IBMにOSを提供するだけでなく、他のメーカーにもライセンス販売を行いました。これにより、「IBM互換機」と呼ばれるPCクローンが次々に登場し、結果的にMS-DOSがパソコン業界の事実上の標準OSとして普及していったのです。
また、「IBM 5150」は拡張性にも優れており、キーボード、プリンター、フロッピードライブ、モニターなどを必要に応じて追加できました。販売価格は、基本構成でおよそ1,565ドル(当時の日本円で約36万円)と決して安価ではありませんでしたが、IBMブランドへの信頼感もあり、ビジネス用途を中心に広く受け入れられていきました。それまでパーソナルコンピューターは、主に技術者や趣味としての利用者が中心でした。しかし、「IBM 5150」の登場により、企業のオフィスや教育機関などにも導入が進み、やがて家庭にも広がっていきました。このようにして、パソコンは一部の専門家の道具から、社会全体の基本インフラへと成長していったのです。
ただし、この成功が皮肉な結果をもたらす一面もありました。オープンアーキテクチャによって互換機メーカーが増えた結果、IBM自身の影響力は徐々に低下し、最終的にはパソコン市場からの撤退を余儀なくされました。それでも、「IBM 5150」の果たした役割は計り知れません。今日、私たちがスマートフォンやノートパソコン、タブレットを当たり前のように使いこなしているのは、この一台の登場があったからこそといえます。オフィスワーク、教育、医療、エンターテインメント──あらゆる分野のデジタル化の始まりは、ここにあったと言っても過言ではありません。
1981年8月12日という日は、単なる製品発表の日ではなく、現代の情報社会が動き出した記念すべき一日なのです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |