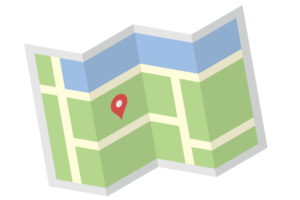一般意味論 2
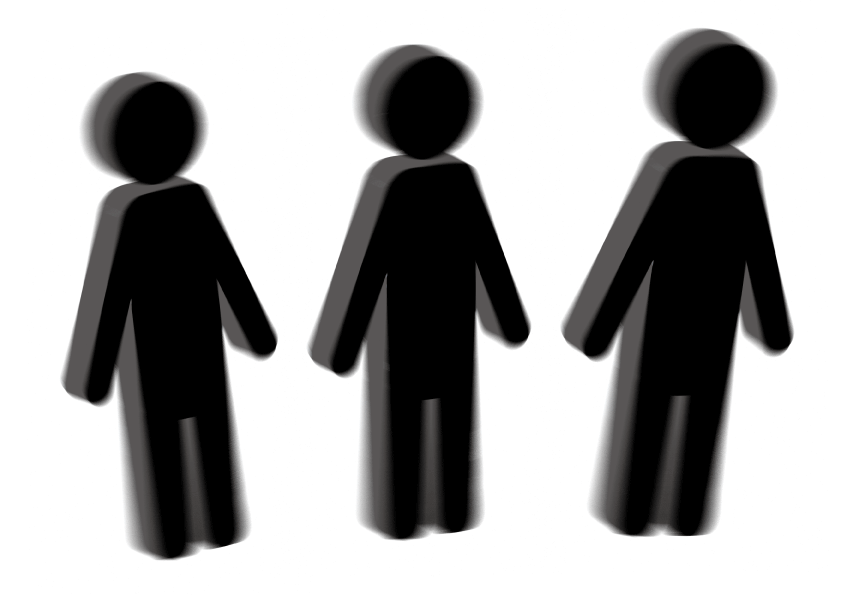
コージブスキーやハヤカワの考え方は現代ではその重要性が増したと思っています。地図はいきなりできるのではなく、現地を見た報告を元に作成します。つまり調査が必要です。正しい地図を創るためには、調査報告が正しいかどうかを見極める能力が必要です。調査者は当然、主観に基づいて報告をしますから、たとえ写真や動画による報告であっても、当然現実からの「切り取り」であって、そこに主観が入ります。現実をみて間違った報告か正しい報告かを判断するのは容易ではなく、報告を盲信するのではなく、現地に対する基礎知識があるとか、自分にも現地体験があるとか、最低でも複数の調査報告を比較するような技術が必要です。調査者が正しい報告をするためには基本的に、第一にそれが実証可能であること。第二にできるだけ推論と断定を排除しなければならないことです。地図を見て現地に行ったら、もう店はなかった、ということでは正しい地図とはいえません。まして、自分の目で確かめず、伝聞をそのまま報告するのは正しくないわけです。現地で評判の店でも、自分で確かめてこそ調査といえます。
実証可能であることは出来ればいいに決まっていますが、必ずしもできるわけではありません。科学的な検証はそれが数値に還元されなければ行うことができませんから、実証性は高いのです。しかし推論と断定はある程度自分でコントロールすることができます。たとえば、目の前をふらふらと走っている車がいたとして、「酔っ払い運転だ」決めつけることは、間違っているかもしれない推論と間違っているかもしれない断定です。つまり間違っているかもしれない地図で、現実はただふらふらと動いている車がいるにすぎません。しかし危険だという判断は正しい予測です。
強い先入観を持った人は良い地図を作ることはできません。なぜなら特定の先入観を持った人にとっては、たとえばヨーロッパは何事においても日本より優れていると思っている人は、落ちているゴミさえ、すばらしいと思うかもしれません。いわゆる「贔屓(ひいき)の引き倒し」になってしまいます。よりすぐれた地図を書ける人は、物事を多面的に見ることができる人です。
一般意味論では、もし混同してしまいそうな場合に、とても役立つ方法が紹介されています。たとえば、目の前に牛がいます。その横にも牛がいます。それらは二頭とも牛という言葉で表されますが、別の個体です。そこで左の牛を牛1、右を牛2とします。これをすべてに当てはめるのです。たとえば、ずるがしこくて人の文化をパクリまくる人々がいたとします。その時想定しているその一人の人は人1のことであって人2や人3とは本来、何の関係もありません。それをまとめて「人はずるがしこい」というのは正しい判断とはいえません。しかし私たちはよくこういう間違いを犯します。ある特定の人に「ずるがしこい」というレッテルを貼って、その人を含む集団をすべて「ずるがしこい集団」と考えることがよくあります。個人を全体と混同するようなことが「間違った地図を頭のなかに持ってしまう」ことがあることに注意しなければなりません。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |