清明
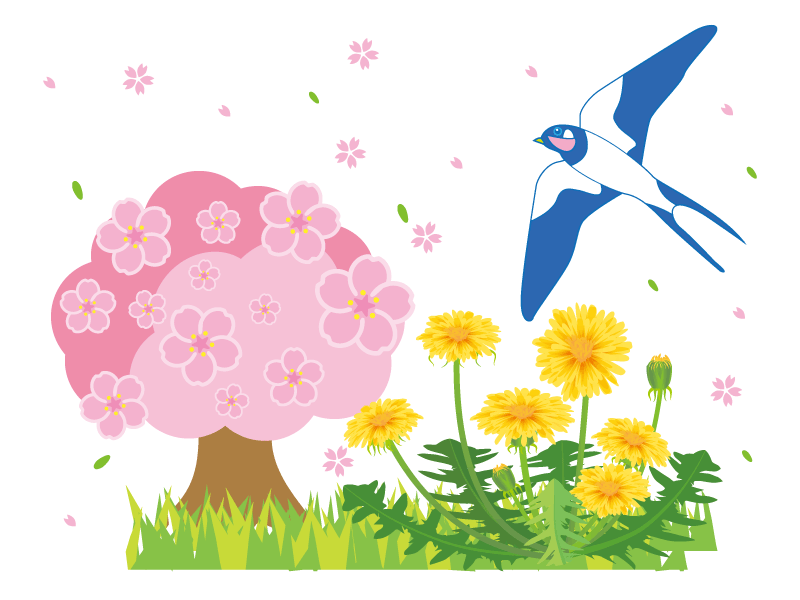
清明(せいめい)は季節の変わり目を表す二十四節気のひとつです、定気法という原理で、太陽黄経が15度のときと定義されており、2025(令和7)年は4月4日に該当します。正確には中央標準時4月4日 21時49分です。
4月の初旬は桜ばかりが話題になりますが、草木が芽吹き、すべてのものが清らかで生き生きしている、という意味合いからその名が付いております。期間としては、次の節気の「穀雨」(こくう)前日までとなります。最近、有名になったネモフィラも見頃を迎え、今では少なくなったザゼンソウの自生が見られる地域もあります。公園で桜を見るついでに小さな草花に目を向けてみると、何か発見があるかもしれません。
「清明」を花言葉にする花はキンポウゲ科デルフィニウム属のヒエンソウ (Delphinium ajacis) があります。中国の清明節は祖先の墓に参り、草むしりをして墓を掃除する日であり、「掃墓節」とも呼ばれています。また、春を迎えて郊外を散策する日であり、「踏青節」とも呼ばれているそうです。『白蛇伝』では、許仙と白娘子が出会ったのも清明節でにぎわう杭州の郊外が舞台でした。また清明節前に摘んだ茶葉を「明前茶」、清明から穀雨までの茶葉を「雨前茶」、穀雨以後の茶葉を「雨後茶」といい、緑茶は清明節に近い時期に摘むほど、香りと甘みがあり、高級とされています。また、古代の寒食節の影響で特定の期間だけ火を使わず料理を作る風習が残っている地方がわずかながら存在するそうです。火を使わない料理というのは世界中に存在し、大昔の貧しい食習慣を忘れないための行事として宗教的に残っています。
沖縄にはこの中国の清明節の影響があり、沖縄本島、伊是名島、伊平屋島、慶良間諸島等では「清明祭」があり、「シーミー」(首里では「ウシーミー(御清明)」)と呼ばれています。中国の風習と同様にお墓の掃除をするとともに墓参を行い、まるでピクニックのような雰囲気で親類が揃って墓前で祖先と共に食事(餅や豚肉料理、お菓子、果物など)を楽しみます。そのために沖縄のお墓の前は広く作られています。内地の「お盆」のような感じです。シーミーが行われない地域もあり、奄美群島、沖縄本島北部(国頭、伊江島)、久米島、先島諸島)では、「十六日祭」(ジュウルクニチ、旧暦の1月16日)または旧暦の七夕(旧暦7月7日)が代わりに行われています。清明七十二候は、空に関わる記述が多く見られます。
初候:玄鳥至(つばめ いたる) :
燕が南からやって来る頃です。越冬する燕もいますが、本来は渡り鳥で、冬の間は暖かい南の地方に移動して過ごします。こうした渡り鳥が、鳥インフルエンザのウイルスを運ぶことも多く、最近では、注意するべき時期になっています。
次候:鴻雁北(こうがん きたす) :
雁が北へ渡って行く。冬にやってきた雁は北に帰ります。北に帰るので、北帰行と呼ばれ、それにちなんだ歌にもなっています。
末候:虹始見(にじ はじめて あらわる) :
雨の後に虹が出始める。虹が出るためには、空気中に水分があり、太陽の位置がある程度高くなる必要があります。この季節に二重の虹が見えることもあります。幸運の象徴だそうです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


