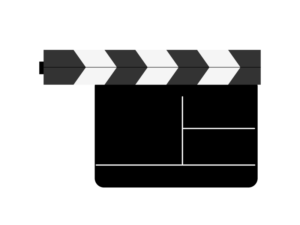五榜の掲示

4月12日は旧暦3月15日に当たります。明治元年(慶応4年)3月15日、明治政府は「五榜の掲示(ごぼうのけいじ)」を発布しました。太政官が立てた五つの高札で、明治政府が民衆に対して出した最初の禁止令です。
その後、いろいろな詔勅などが出て6年後には廃止されますが、その内容は引き継がれていきます。基本的には江戸時代の倫理規定をほぼ踏襲したもので、「第一札から第三札、即ち、第一札による五倫(君臣の義、父子の親、夫婦の別、長幼の序、朋友の信。端的には天皇や家父長に対する忠孝)や憐れみの推奨および悪業の禁止、第二札による徒党・強訴・逃散(集団で謀議を計ること)の禁止、第三札による切支丹・邪宗門の禁止は、いずれも江戸幕府の統制をそのまま踏襲したものである。第四札は、明治新政府独自の万国公法の履行と外国人殺傷の禁である。第五札は、古代律令制の復活を彷彿とさせる脱籍浮浪化に対する禁であり、これも明治政府的なものである。」(Wikipedia)
第1札にある「五倫(ごりん)」とは、儒教における5つの道徳法則、および徳目のことで、主として孟子によって提唱されたものです。内容は「父子の親(しん):父と子の間は親愛の情で結ばれなくてはならない。「君臣の義」:君主と臣下は互いに慈しみの心で結ばれなくてはならない。「夫婦の別」:夫には夫の役割、妻には妻の役割があり、それぞれ異なる。「長幼の序」:年少者は年長者を敬い、したがわなければならない。「朋友の信」:友はたがいに信頼の情で結ばれなくてはならない。孟子は、以上の五徳を守ることによって社会の平穏が保たれるのであり、これら秩序を保つ人倫をしっかり教えられない人間は禽獣に等しい存在であるとした(同上)
現在、こういう主張をすれば、右翼とか古いとか批判されますが、日本の伝統文化の中にはまだかなり残っています。父子を親子と置き換え、君臣を上司と部下に置き換えれば、今もそう思っている人は多いと思います。また、夫婦の在り方は、今は別性問題も含めて、家事分担が進んで変化してきていますが、その背景には共働きと専業主婦への蔑視があります。長幼の序は遺産問題で揉めることの原因にもなっています。またシルバーシートやシニア優先の根本になっています。友達が信頼し合うことに反対する人は今もいないでしょう。現代では、逆にこうした倫理観が薄れたことが社会問題となってきています。一方で、カトリック教会は「人はいかに五倫の道を完うしても、宗教をゆるがせにしては、人の道に欠けるところがあるのであります」「それゆえ、宗教を離れた社会秩序や道徳は、その根底を失ったものであって、実践的には甚だ不完全であると言わねばなりません」と五倫を部分評価はしつつも、全ての徳は神に根差すので、信仰がなければ不完全で不安定であるとしている(同上)そうです。道徳の上に信仰がある、というわけです。実はカトリックの倫理観はさらに厳しいものです。それでカトリック教圏の社会と治安が安定しているか、というとそうでもありません。欧米の保守派は非カトリック的な倫理観を主張していますが、このアジア的倫理観とは違いがあります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |