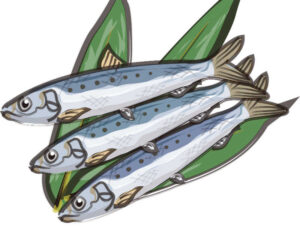入定
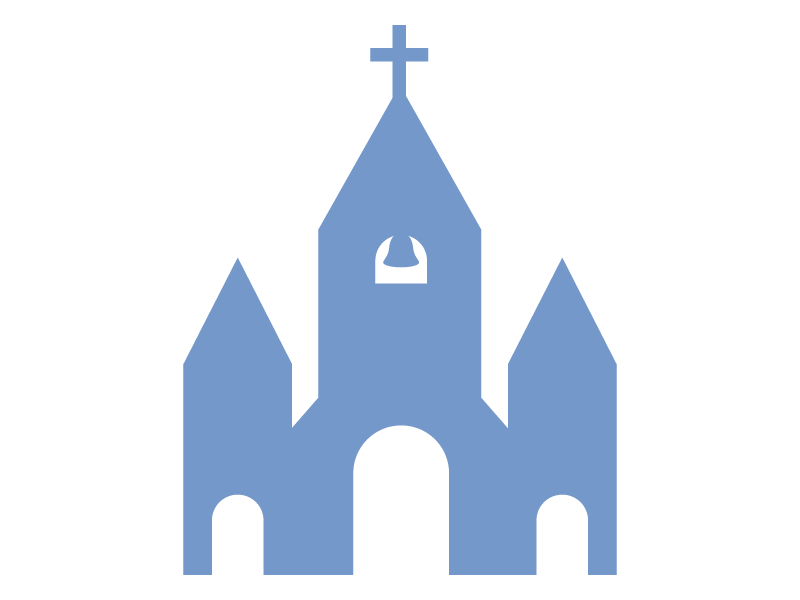
慶長17年(1612年)3月21日、江戸幕府は幕府直轄領にキリシタン禁教令を発令し、翌年全国に拡大していきました。また承和2年(835年)の同日、真言宗の開祖である空海(弘法大師)が亡くなりました。これを入定(にゅうじょう)と呼んでいます。
入定は、真言宗に伝わる伝説的信仰で、元の意味は「禅定(ぜんじょう)に入る」という意味ですが、弘法大師が永遠の瞑想に入っているという意味になっていて、多くの宗教に見られる奇跡のようなものです。それを信じることが信仰ということです。空海は、生死の境を超え弥勒菩薩出世の時まで、衆生救済を目的として永遠の瞑想に入り、現在も高野山奥之院の弘法大師御廟で入定していると信じられています。そこで、高野山金剛峰寺では、「生身供(しょうじんぐ)」という、入定後から現在まで1200年もの間続けられている儀式があります。奥之院の維那(ゆいな)と呼ばれる仕侍僧が1日2回、御廟の空海に衣服と食事を届けることが行われています。霊廟内の模様は維那以外が窺うことはできず、維那を務めた者も他言しないため部外者には実態は秘密のままです。また、入定したあとも諸国を行脚している説もあり、その証拠として、毎年3月21日に高野山の宝亀院が行う空海の衣裳を改める儀式の際、衣裳に土がついていることがあげられています。信仰に伝説はつきものですが、事実であるかどうかよりも、儀式が続けられる中で真実になっていくことがしばしばあります。唯物論的な視点から批判することは無意味でしょう。これら2つの重要な宗教関係が同日というのは偶然ですが不思議です。
江戸幕府のキリシタン禁教令は、今日的視点からすると、カトリックもプロテスタントも一括りになっていて、西洋事情にも詳しかったはずの江戸幕府にしては、不思議な感じもします。「キリシタン」はポルトガル語で「キリスト教徒」を指す言葉であり、英語の「クリスチャン」(Christian)に該当します。ポルトガル語ではキリスト教徒全般を指すのですが、日本では戦国時代以後、日本に伝来したキリスト教の信者、伝道者またその働きを指しています。現在の日本では、「キリシタン」という言葉は「キリシタン大名」や「隠れキリシタン」など、日本の歴史用語として使用されており、現代日本のキリスト教徒を指す場合は「クリスチャン」を用いることになっています。江戸幕府はプロテスタントとカトリックの教義は同じもので、教派の違いは重要でないとし、オランダ人もキリシタンであると認識していたようです。キリスト教圏からみれば、仏教を一括りですし、現在でもイスラム教は一括りにしていますから、あながち江戸幕府が無知とはいえません。徳川家光はオランダ人の宗教がポルトガル人の宗教と類似したものであると理解していたようで、オランダ人を長崎の出島に監禁した理由の一つにキリスト教の信仰があったということになっています。キリスト教禁令はローマカトリック教会に限定されていたわけではなく、平戸のオランダ倉庫はキリスト教の年号を使用したことを理由に破壊され、オランダ人墓地も同時期に破却、死体は掘り返され海に投棄されました。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |