日本のリサイクルの歴史
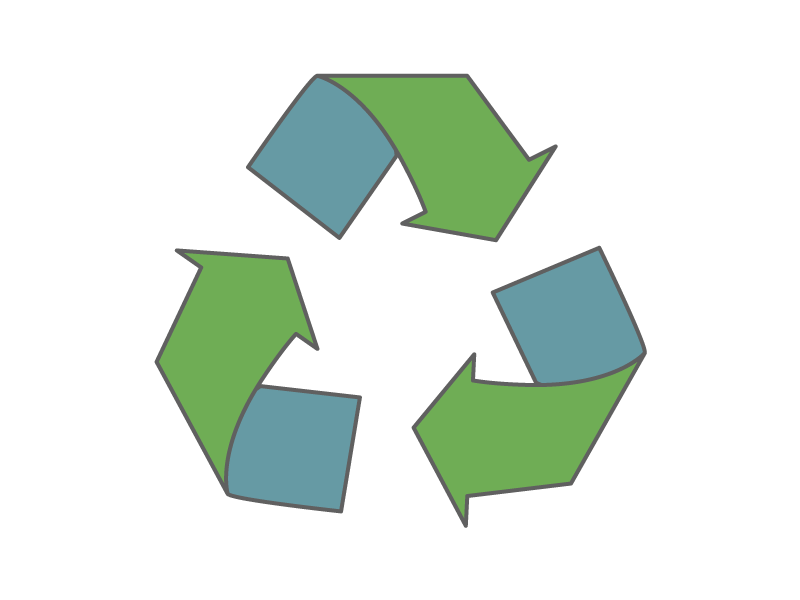
元禄9年(1696)3月29日(旧暦) 江戸幕府は江戸市中のごみを利用した埋立てを許可しました。それが現在の永代島です。
ゴミを埋めて土地にする、という発想は近代的なものと誤解されていますが、江戸時代からあったのです。江戸時代は相当なリサイクル社会でした。この時代は実に物を大切にしていました。下駄は鼻緒が切れれば布か紐で代用し、どうしてもダメなら新しい鼻緒と取り替えます。下駄の歯が減れば歯だけを取り替え、台がダメなら台だけ取り替える。こうしてダメになった部分だけを交換し使える所は最後まで使いきるということが当たり前でした。また片方を無くせば、残りの片方をボロ市に出し、買った人もそれに合う片方を見つけ組み合わせて履きます。それでも使い道が無くなると最後には燃料として利用しました。これが今も続く「勿体ない」思想です。
「もったいない」の語源は、仏教用語の「物体(もったい)」に由来しています。 「物体」とは「物のあるべき姿・物の本質的なもの」という意味です。現代読みの「ぶったい」とは意味が異なります。 「もったいない」は「物体」を否定する言葉なので、「物のあるべき姿がないことを嘆き惜しむ」という意味があります。物の一部が欠けたなら、そこを補充して「元のあるべき姿にする」という思想です。今流行りの断捨離の正反対の思想です。その勿体ない思想が染み込んでいる人はなかなか物が捨てられないわけです。しかし、ただ置いておくだけでなく、元の形に戻して活用しなければなりません。その1つがリサイクルの思想です。現代では「環境に優しい」という理由になっていますが、本来はそうではないことを改めて知っておきたいところです。
江戸時代は、物は徹底的に再使用、再利用ができるリサイクルの組織が社会的に整っていました。 つまりリサイクルが一つの産業として成立され、大勢の職人や商人がリサイクル業で生計を立てていました。「羅宇屋[らうや](羅宇とはキセルの火皿と吸い口をつなぐ竹)」「箍屋[たがや]」「鋳掛屋」「古着屋」「古鉄買い」「紙屑買い」などがそれにあたります。今でもたまに見かける「包丁研ぎ」などもありました。「村の鍛冶屋」は農機具の修理をしていました。「時計屋」は修理が主でした。
現代から見ると驚きなのがトイレです。江戸の町では、し尿(下肥)は近郊農村に肥料として売買されていました。つまりし尿のリサイクルです。最初は江戸の町でも、し尿は川端につくってある雪隠(せっちん)から川や堀に流していましたが、雪隠を小屋とともに取り壊すよう命じた法令が出されたため、公共のトイレが無く不便でした。しかし近郊農村の下肥の需要が高まると、積極的に収集する方法が考えられるようになり盛り場には有料の貸雪隠なども設けられました。また町の各所には樽や桶を置いただけの簡易トイレが設置されました。これは江戸周辺の有力農民が下肥収集のために設置したもので、使用は無料でしたが汲取りをできるのは設置者に限られていました。汲み取り業者は長屋の大家にお金を払って回収していました。食生活の貧しい庶民のは安く、栄養のよい武家のし尿は高かったそうです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


