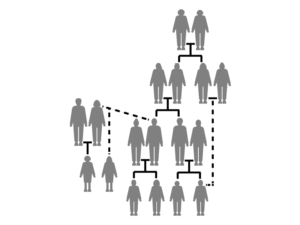聖徳太子と十七条憲法

推古12年(604)聖徳太子が十七条憲法を制定しました。今から1421年前のことです。英国憲法の礎といわれるマグナ・カルタの制定は1215年ですから、それより611年も前のことです。日本はもっとこれを誇りにしてもよい、と思われます。全部は紹介しきれませんが、現代語訳で読んでみると、現代にも通用する教えであることがわかります。Wikipedia から一部引用します。
第1条:おたがいの心が和らいで協力することが貴いのであって、むやみに反抗することのないようにせよ。それが根本的態度でなければならぬ。ところが人にはそれぞれ党派心があり、大局をみとおしているものは少ない。だから主君や父に従わず、あるいは近隣の人びとと争いを起こすようになる。しかしながら、人びとが上も下も和らぎ睦まじく話し合いができるならば、ことがらは道理にかない、何ごとも成しとげられないことはない。
第2条:まごころをこめて三宝をうやまえ。三宝とはさとれる仏と、理法と、人びとのつどいのことである。それは生きとし生けるものの最後のよりどころであり、あらゆる国々が仰ぎ尊ぶ究極の規範である。いずれの時代でも、いかなる人でも、この理法を尊重しないことがあろうか。人間には極悪のものはまれである。教えられたらば、道理に従うものである。それゆえに、三宝にたよるのでなければ、よこしまな心や行いを何によって正しくすることができようか。
第3条:天皇の詔を承ったときには、かならずそれを謹んで受けよ。君は天のようなものであり、臣民たちは地のようなものである。天は覆い、地は載せる。そのように分の守りがあるから、春・夏・秋・冬の四季が順調に移り行き、万物がそれぞれに発展するのである。もしも地が天を覆うようなことがあれば、破壊が起こるだけである。こういうわけだから、君が命ずれば臣民はそれを承って実行し、上の人が行うことに下の人びとが追随するのである。だから天皇の詔を承ったならば、かならず謹んで奉ぜよ。もしも謹んで奉じないならば、おのずから事は失敗してしまうであろう。
第4条:もろもろの官吏は礼法を根本とせよ。そもそも人民を治める根本は、かならず礼法にあるからである。上の人びとに礼法がなければ、下の民衆は秩序が保たれないで乱れることになる。また下の民衆のあいだで礼法が保たれていなければ、かならず罪を犯すようなことが起きる。したがってもろもろの官吏が礼を保っていれば、社会秩序は乱れないことになるし、またもろもろの人民が礼を保っていれば、国家はおのずからも治まるものである。(https://ja.wikipedia.org/wiki/十七条憲法より引用)
いかがでしょうか。今の法律体系は「~してはいけない」といった犯罪防止的なものばかりですが、肯定的な表現で人々の心の在り方を説いた憲法は現代憲法とは違う意味で重要な規範となっています。人心が乱れている今こそ、勉強しなおすのがよいとは思われませんか。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |