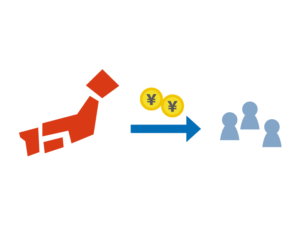無血開城

明治元年(1868)4月11日(旧暦)、江戸城の無血開城が行われました。これは「話し合いにより流血を避けた」という美談として知られています。しかし、現代の目で見れば「無条件降伏」と同じです。無血開城というと、本件のことを意味しますが、一般的には明け渡しであり、戦わずして城を明け渡すことは何度もありました。
有名な例をとしては、「赤穂浪士」に出てくる、赤穂城の明け渡しです。浅野家が改易になって、家臣はみな城を出て、屋敷を出て、領外に離散する噺です。領内に浪人として留まることができないわけではないようですが、城は受城使の龍野藩主・ 脇坂安照と足守藩主・木下公定に引き取られました。当初、藩内で主戦派もいて、籠城して幕府軍と戦おうと人々を説得し、大石内蔵助は明け渡しを決意します。この場合は、藩内の話合いであって、敵との交渉ではないことが、幕末の無血開城とは異なります。
「無血開城」は後代の歴史家が名づけたものです。一般的には、赤穂城と同じくお城の「明け渡し」でした。西郷隆盛と勝海舟も、2日間にわたる交渉の席ではこのことばを使っていたそうです。この「明け渡し」という表現は徳川期を通じて、その実例は全国にありました。徳川時代は幕府による「おとりつぶし」「国替え」が日常茶飯事でしたが、それは徳川期を通じて、幕府権力はおおむね絶大だったことにあります。全国の大名から所領を没収することも、あるいは彼らを別の土地へ移動させることも容易でした。前者は改易、後者は転封といいます。もしくは前者は「おとりつぶし」、後者は「国替え」ともいいました。統計によれば改易はぜんぶで200件以上、転封は300件以上あったそうです。なかば日常茶飯事であって、これらの実行には、当然、城の明け渡しがともなうわけで、ほとんどの場合、じつに平和裡におこなわれてきました。
しかし、幕末の場合、無血開城後に血が流れました。5月15日の上野戦争で、天野八郎ら彰義隊が寛永寺で抗戦しました。そして7月29日の北越戦争で、河井継之助ら長岡藩兵が長岡城で抗戦しました。そして9月22日の会津戦争で、松平容保ら会津藩兵が若松城で抗戦しました。白虎隊の悲劇は有名です。さらに翌年の5月18日に箱館戦争で、榎本武揚ら旧幕兵が五稜郭で抗戦しました。新選組の土方歳三が戦死し、この話もいろいろなドラマになって有名です。この日をもって旧幕側は全敗したわけです。
現代の感覚だと、「どうせやるなら、なんで開城前にやらなかったのか」ということになります。そのほうが兵力の分散も避けられたし、戦術的には失敗といえそうです。将軍家の禄を食んでいたのに、いざその危急のときに指をくわえて敵の城入りを眺めておりました、というのは、後世はもちろん、同時代でも、かっこ悪いことです。しかし、江戸時代に城明け渡しが頻繁にあり、平和的に事を運ぶほうが当たり前なのだと思っていたのです。開城前に戦争すべしという発想がなかったのかもしれない。しかし実際に事が起きてみると、中央でのこの出来事がとんでもないことになったのだと、後から気づいたのかもしれない。中央と地方の意識差は今もあります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |