孔子
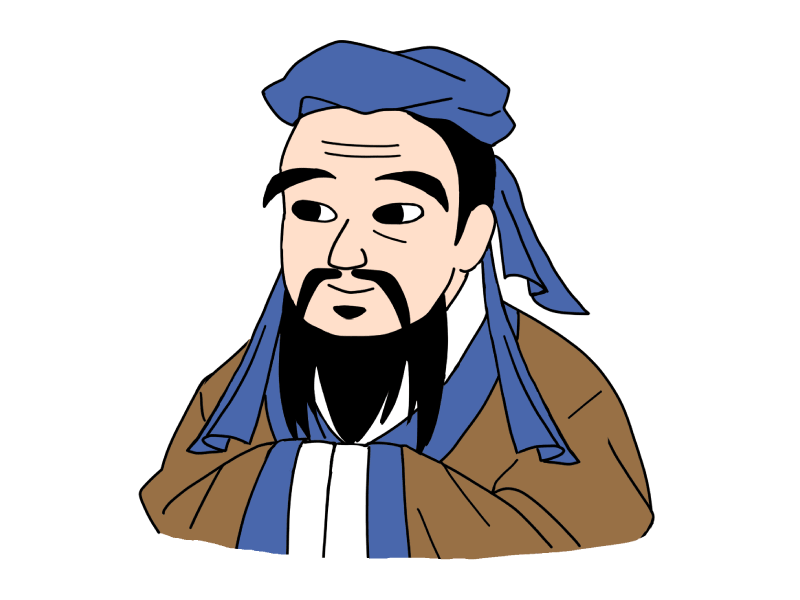
紀元前479年4月18日(旧暦)孔子がなくなったとされています。旧暦なのは紀元前ですから、当然です。孔子(こうし)は(くじ)とも読むそうです。中国語の拼音では Kǒng zǐ (こんじ)と読むそうで、英語ではConfucius [kənˈfju.ʃəs](コンフューシャス)といいます。生まれは紀元前552年または紀元前551年です、春秋時代の中国の思想家として有名で、儒教の始祖です。孔子というのは尊称です。日本では昔、論語が必須科目であったこともあり、有名です。
孔子の弟子たちは孔子の思想を奉じて教団を作り、戦国時代、儒家となって諸子百家といわれる一家をなしました。孔子の死後約400年かけて孔子の教えをまとめ、弟子達が編纂したのが『論語』です。宗教的な聖書だけでなく、名著と呼ばれる作品の多くは、こうした弟子たちによる編纂が多く見られます。キリスト教の聖書や仏教の経典もそうした名著の一つです。
約3000人の弟子がおり、特に「身の六芸に通じる者」として七十子がいました。そのうち特に優れた高弟は孔門十哲と呼ばれ、その才能ごとに四科に分けられています。それは徳行(顔回など)、言語(子貢など)、政事子路など)、文学(学問のこと))(子游など)の四科です。その中でも子路と孔子のやり取りが論語のなかでは1番多いとされています。その他、孝の実践で知られる『孝経』の作者とされる曾子、その弟子には孔子の孫で『中庸』の作者とされる子思がいました。孔子の死後、儒家は八派に分かれます。その中で孟子は性善説を唱え、孔子が最高の徳目とした仁に加え、実践が可能とされる徳目義の思想を主張しました、荀子は性悪説を唱えて礼治主義を主張しました。『詩』『書』『礼』『楽』『易』『春秋』といった周の書物を六経として儒家の経典とし、その儒家的な解釈学の立場から『礼記』や『易伝』『春秋左氏伝』『春秋公羊伝』『春秋穀梁伝』といった注釈書や論文集である伝が整理され、最終的な完成は漢代になってからです。江戸時代後期の曲亭馬琴による『南総里見八犬伝』に出てくる「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌の文字のある数珠の玉(仁義八行の玉)」の八行は儒教の教えですし、NHKの「べらぼう」に出てくる「忘八」とはこの八つの徳目を忘れた人、という意味です。性善説や性悪説は今も使わる表現ですし、日本文化の中に深く儒教の思想が入り込んでいることがわかります。
時々、お隣の韓国が儒教の国といわれることがありますが、無宗教の人口が過半数で、キリスト教が3割、仏教が1割程度で、儒教的な側面は生活習慣として残っているものの、宗教的には残っていないに等しいです。そして儒教の発祥の地である、中国では1910年代の新文化運動では、儒教への批判が展開され、1949年に成立した中華人民共和国では、1960年代後半からの文化大革命で、毛沢東とその部下達は孔子と林彪を結びつけて批判する運動を展開し、孔子は封建主義を広めた中国史の悪人とされました。近年、中国共産党が新儒教主義また儒教社会主義を提唱し、「孔子学院」のようにブランド名として活用されるように変化してきています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


