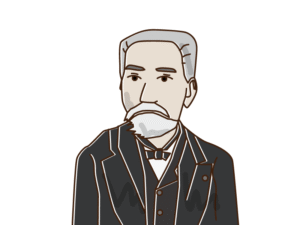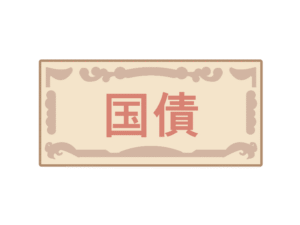千代田の刃傷
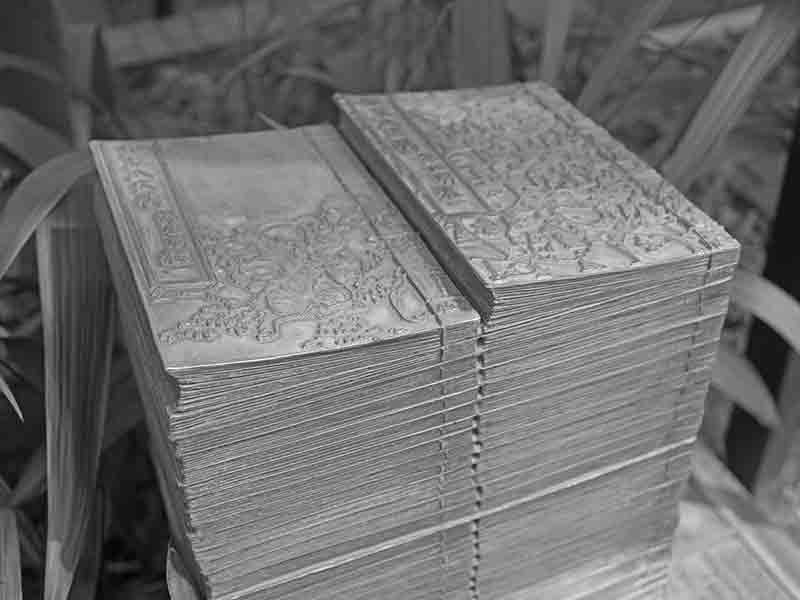
江戸城内での刃傷(にんじょう)沙汰といえば、忠臣蔵の「松の廊下」が有名ですが、実は何度もこうした刃傷沙汰が起きています。千代田の刃傷は、文政6年(1823)4月22日(旧暦)に松平忠寛(外記)によって引き起こされた刃傷事件です。
西の丸の御書院番の新参・松平忠寛(松平外記)は、古参の度重なる侮罵と専横とに、ついに鬱憤これを抑えることができず、本多伊織、戸田彦之進および沼間左京の3人を殿中において斬り殺し、間部源十郎および神尾五郎三郎の2人には傷を負わせ、間部は深手により翌日死亡、自らは自刃し果てたものです。事件発生後に直接の上司である酒井山城守を交えて、事件を隠蔽する工作が行われ、目付は正式な見分書には死者が出た事を記載せず、後の保身のために真実を記した文書を封印文書として作成しました。本丸から来た侍医は死亡者を危篤状態と偽るために外科的工作と虚偽報告するように頼まれ、一旦は拒んだもののこれに従いました。血で染まった20畳の畳は深夜のうちに取り替えられました。加藤曳尾庵の『我衣』によれば、外記が大奥に務める伯母に鬱憤を吐露した遺言ともいえる書き置きを渡していたため、大奥を通じて事件が露見したということのようです。こうした不祥事は隠蔽されるのが昔からの歴史です。時の老中・水野忠成が厳重詮議を行い、殺害された3人の所領は没収され、神尾は改易を申し渡されました。なお、松平家は忠寛の子栄太郎が相続を許されました。
しかし、事件の顛末は瓦版で報じられ、江戸町民も知るところとなり、落書も数多く作られました。今なら週刊誌による報道とネットの拡散、というところでしょうか。市井の人々は外記を取り押さえる事も出来ず、凶刃から逃げ惑った旗本の不甲斐なさを物笑いの種としました。この事件は曲亭馬琴らの『兎園小説余録』にも収められ、歌舞伎狂言にもなりました。江戸城内での刃傷事件は松の廊下とこの事件以外に、寛永五年(1628)8月 豊島明重事件、貞享元年(1684)8月 稲葉正休事件、享保十年(1725)7月水野忠恒事件、延享四年(1747)8月 板倉勝該事件、天明四年(1784)3月 佐野政言事件と5件あり、多くは江戸中期以降に起きています。佐野政言事件は、先日のコラムに書きましたし、NHKの「べらぼう」でも描かれるでしょうから、詳しくはそちらにお任せします。もしかすると、この外記事件も描かれるかもしれません。
外記は弓術・馬術に長じ、几帳面で神経質な性格でとても穏やかな人物であったが、実は癲癇性が強く人付き合いが苦手であったとそうです。旗本として11代将軍・徳川家斉に仕え、書院番士として蔵米300俵で働いていました。当時、旗本の風紀は乱れており、番士の中でも新人・古参の区別は厳しく新参者はまるで奴隷のように酷使虐待されていたそうです。外記がいた西丸書院番の酒井山城守組では、古参による新参者へのいじめが横行することで有名な職場でした。その中で外記は常に己が正義と信じるところを主張し、いささかも屈することがなかったためにますます古参たちから疎まれたのです。今もどこかの職場でありそうなパワハラ事件ですね。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |