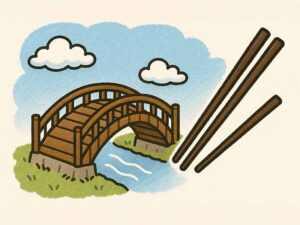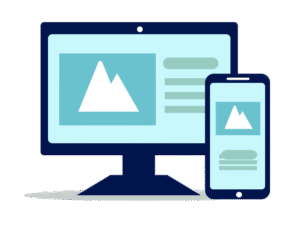アメリカと日本の所得税の歴史

現代の私たちの生活に密接に関わる所得税ですが、その背後には国家の在り方、戦争、社会制度の変遷が複雑に絡み合っています。特に注目すべきは、1861年8月5日、アメリカ合衆国で初めて所得税制度が導入されたということです。この歴史的な出来事は、税制の面から国家の成長と危機管理能力を如実に物語っています。アメリカの所得税導入は、南北戦争(1861年–1865年)という未曾有の国家的危機に対応するためでした。リンカーン大統領は、戦費調達のために「所得税法(Revenue Act of 1861)」に署名し、年間800ドルを超える所得に対して3%の課税を実施しました。これはアメリカ史上初めての連邦レベルでの所得課税であり、国家による徴税の直接的な形態として注目されました。この制度は、あくまでも「臨時措置」とされていましたが、戦後も収入の安定源として重視され、後の1894年に再び連邦所得税法が成立します。そして1913年、憲法修正第16条の批准により、所得税制度はアメリカに恒久的に定着しました。こうした制度化の過程は、「税とは国家と国民の信頼関係に根ざす」という民主主義の原理を反映しています。
日本における所得税制度は、明治20年(1887年)に初めて導入されました。これは、明治政府が近代国家としての財政基盤を確立するための一環であり、地租・営業税に次ぐ「第三の柱」としての役割を担いました。もともと明治初期の税制は土地課税中心であり、人口増加や経済成長に見合う制度としての限界がありました。1887年の「所得税法」は、イギリスの制度を参考にしており、課税対象は地代、利子、俸給などの所得に分けられ、累進的な税率が導入されました。とはいえ、導入初期の所得税は限られた富裕層のみを対象とする制度で、一般庶民への影響は小さかったといえます。しかし、日清戦争(1894年–1895年)と日露戦争(1904年–1905年)を経て、戦費調達と財政安定のために、所得税は拡充されていきます。特に、第一次世界大戦後の経済不安や関東大震災などの国家的危機を契機として、税制改革が断続的に行われ、やがて「納税者」の裾野は着実に広がっていきました。
アメリカも日本も、所得税の導入には「戦争」や「財政危機」といった国難が関わっていました。逆説的にいえば、税制とは国家の「非常時の器量」を試す制度ともいえるのです。と同時に、制度の定着には、国民の理解と参加が欠かせません。こういう視点は現在、忘れられているようで、税を扱う財務省や政府は非常時という観念がすっかり抜け落ちています。所得税はまた、社会の階層や格差、労働と富の配分をどうとらえるかという思想的な問題とも直結します。例えば、アメリカでは20世紀半ばから所得税率が段階的に引き下げられ、今日では「富裕層への課税が緩すぎる」という批判が根強くあります。一方、日本では平成以降の消費税拡大に対し、所得税の負担軽減が進められる傾向にあり、所得再分配機能が十分かどうかが議論されるようになりました。
税金はその成り立ちを知ることで、国家の構造と社会をより深く理解できるようになります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |