ワールド・ワイド・ウェブ(www)が世界を変えた
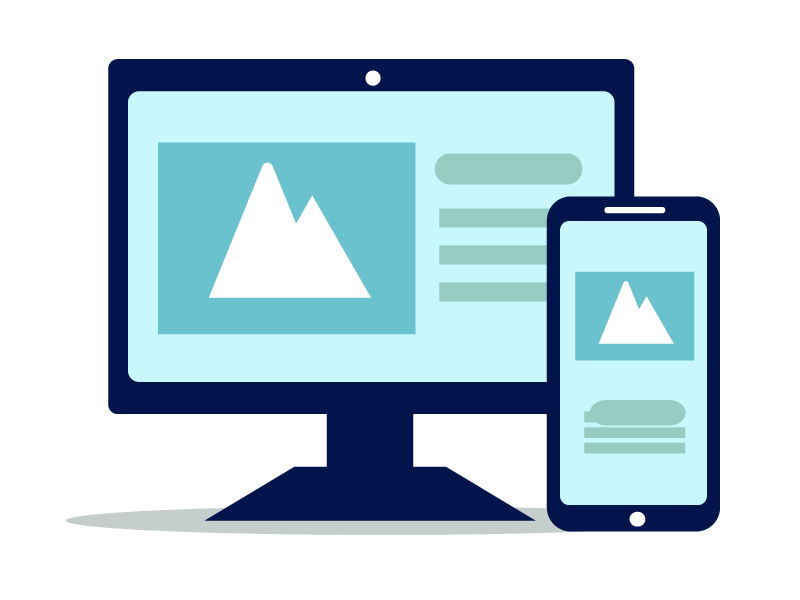
8月6日というと、まず原爆の日が頭に浮かびますが、この日は現代のネット社会を作りだした元ともいえるwwwの日でもあります。スイス・ジュネーブ郊外にある欧州合同原子核研究機関(CERN)において、ある技術がひっそりと公表されました。それが、今日のインターネットの中核をなす「ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)」、いわゆるウェブの誕生です。発案者は、イギリス人の計算機科学者ティム・バーナーズ=リー。彼が当時所属していたCERNでは、物理学者たちが膨大な研究データや論文を共有するための効率的な手段を必要としていました。バーナーズ=リーは、そのための解決策として「ハイパーテキスト」と「インターネット通信」を組み合わせ、ひとつのシステムを構築しました。それが後の「ウェブ(web)」と呼ばれる仕組みであり、我々が普段使っている http:// や HTML(ハイパーテキストマークアップ言語)、そして「ブラウザ」の原型も、彼の手によって生まれました。
ここでよく混同されがちなのが、インターネットとウェブの違いです。インターネットは、もともと1960年代後半に米国防総省の研究から始まり、複数のコンピュータ同士を接続するための「ネットワークのネットワーク」でした。一方、ウェブはその上に乗る情報の共有・閲覧の仕組みであり、インターネットを「道路網」だとすれば、ウェブはその上を走る「車」や「案内標識」にあたります。つまり、バーナーズ=リーが作り出したのは、インターネットという広大な空間の中で、情報を誰でも手軽に「見る」「渡す」「探す」ための仕組みだったのです。
この区別は、私たちの現在の生活にも深くかかわっています。メールやチャット、アプリケーションはインターネットを利用していますが、ウェブとは別の技術です。SNSやオンラインショップ、ブログなど、「見る・読む・探す」タイプのサービスは、ほぼ全てウェブ技術の恩恵を受けているのです。バーナーズ=リーが1991年に初めてウェブを世界へ公開したとき、表示できるのはただのテキストとリンクだけでした。画像も動画も音声も、まだ扱えませんでした。しかしその後、モザイク(Mosaic)、ネットスケープ(Netscape)、インターネットエクスプローラー(IE)といったブラウザの登場により、ウェブは一気に視覚的な表現力を増し、1995年ごろから「インターネットブーム」として世界中に普及していきました。現在では、HTML5やJavaScriptなどの進化により、動画配信、音声通話、3Dアニメーション、そしてAIとの対話までもがウェブ上で可能となっています。Google、Amazon、Facebook(現Meta)、YouTube、ChatGPTなど私たちが日常的に利用している多くのサービスが、このウェブの仕組みの上に成り立っています。
ウェブの登場は、情報の民主化をもたらしました。それまでは一部の学者や政府関係者しかアクセスできなかった情報が、誰もが閲覧・発信できるものになったのです。教育、医療、政治、娯楽、すべての分野でウェブは不可欠な存在となりました。1991年8月6日は、人類の情報文明における大きな転換点でした。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


