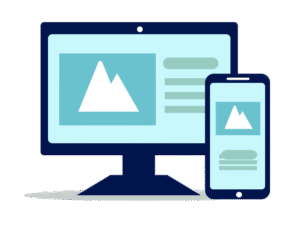立秋 ― 暦のうえで秋が始まる日

日本の季節は、古来より、季節の変化をより細やかに捉えるために考案されたのが二十四節気です。そのひとつである 「立秋(りっしゅう)」は、文字通り「秋の始まり」を告げる節目の日として、今なお暮らしや文化の中に息づいています。今年の立秋は 8月7日。この日を境に、暦のうえでは秋に入ります。とはいえ、実際には連日の猛暑が続き、涼しい風や秋の気配を実感するには程遠い状態です。それでも、立秋には独特の意味と風情があります。
立秋は、太陽黄経が135度に達した瞬間を基準に定められており、毎年8月7日ごろに訪れます。二十四節気の中では13番目にあたり、春夏を終えて秋に入る折り返し点にあたります。この日以降に吹く風を「秋風」、虫の音も「秋の声」と呼ばれ、季語としても秋が立ち始めたことを感じ取る材料となります。また、立秋を過ぎてからの暑さは残暑(ざんしょ)と呼ばれ、暑中見舞いもこの日を境に「残暑見舞い」へと切り替えるのが日本の習わしです。このように、立秋は単なる暦の節目ではなく、季節の移り変わりを繊細に感じ取るための文化的なセンサーとも言えます。
立秋を迎えるころ、日本列島はまだ盛夏のさなか。35度を超える猛暑日が続き、蝉の鳴き声も勢いを失いません。ところが、注意深く自然に目を向けると、確かに小さな秋の兆しが見えてきます。たとえば、朝夕の風にわずかに涼しさを感じる日が出てきたり、空の色が夏の強烈な青から、少しずつ透明感を帯びてきたりします。また、田んぼでは稲がぐんぐんと実りを進め、秋の収穫へ向けた準備が始まります。高原や里山では、ススキの穂やヒグラシの声も聞こえてきて、五感が秋を予感し始める時期なのです。立秋を過ぎると、手紙の書き方にも変化が生まれます。日本には暑中見舞いという季節の挨拶状を送る習慣がありますが、これは梅雨明けから立秋までの間に送るものとされています。つまり、立秋を過ぎたら「残暑見舞い」に切り替えるのが正式なマナーとされています。このような細やかな配慮は、日本人が季節の変化にいかに敏感で、心を通わせるために暦を生活に取り入れてきたかを物語っています。しかし、立秋という言葉にふさわしくないほどの猛暑が続く近年、「本当に秋なの?」と感じる人も少なくありません。しかし、この“ズレ”こそが、日本人が自然と共生してきた証でもあります。農作業を行ううえでは、実際の気温や天気だけでなく、「季節の節目」を意識することが大切でした。立秋は、実際の涼しさを示すものではなく、季節が変わる「方向性」や「流れ」を感じ取るための基準なのです。現代でも、夏バテを感じるこの時期に、秋の準備や体調管理を意識し始めるきっかけとなります。
立秋に特定の大規模行事は少ないものの、地方によっては「初風祈願」「秋初めの虫送り」など、秋の豊穣を祈る伝統行事が行われることがあります。また、京料理や懐石料理の世界では、立秋を境に器や食材の選び方を変えるなど、季節の先取りを大切にしています。さらに、和菓子の世界でも立秋や初秋といった銘を持つ練り切りが登場し、見た目にも涼しさと秋の気配を届けてくれます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |