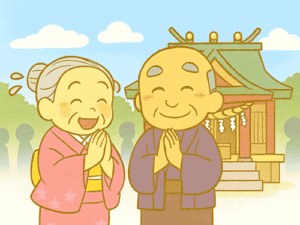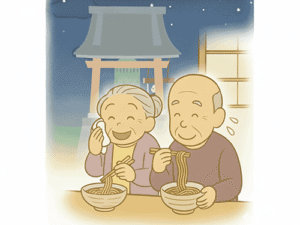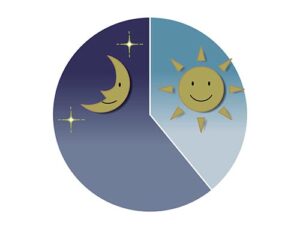その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
旧正月新着!!
今年は2月17日が旧暦元日、旧正月となります。旧正月という言葉は、どこか懐かしい響きをもっています。けれど実際には、これは単なる「昔の正月」ではありません。現在も東アジアを中心に広く祝われている、いわば“もうひとつの時間の始まり”です。 旧正月とは、太陰太陽暦―月の満ち欠けを基準にしつつ、太陽の運行で季節を調整する暦―による新年を指します。中国では春節と呼ばれ、2026年の春節は2月17日頃になり・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
節分会新着!!
立春と節分会は、日本の暦と想像力がもっとも生き生きと交差する季節の結節点です。節分は「季節を分ける」日で、本来は年に四度ありましたが、やがて立春前日の一回が特別視されるようになりました。冬の終わりと春の始まり。その境目は、古来もっとも“ゆらぎ”の大きい時間と考えられ、鬼や疫、災いが入り込みやすいとされます。だからこそ豆をまき、声を張り、身体を動かし、世界の輪郭をはっきりさせる必要があったのです。 ・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
大寒
大寒は寒さの極みが告げる、春への反転点です。一年で最も寒い頃を指す大寒は、二十四節気の最後を飾る節気です。例年一月二十日頃に始まり、次の立春までのおよそ二週間、暦の上では寒さの極みに位置づけられます。文字どおり「大いに寒い」時期ですが、この厳しさは単なる終着点ではありません。むしろ、大寒は春への反転がすでに始まっていることを、静かに示す節目でもあります。実際の気候を見れば、大寒は積雪が深まり、水が・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
冬土用の入り
冬土用の入りは立春を迎えるための「静かな助走」です。暦の上では「冬土用の入り」を迎えます。土用と聞くと、夏の土用丑の日を思い浮かべる方が多いと思いますが、土用は年に四回あります。立春・立夏・立秋・立冬、それぞれの日の直前、約十八~十九日間が土用とされ、その季節から次の季節へと移るための調整期間です。冬土用は、立春を控えた旧暦一年最後の土用であり、寒さの底から新しい循環へと向かう、いわば「静かな助走・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
正月三日
正月三日は、元日や二日に比べると行事の数も少なく、どこか影が薄い存在に見えます。しかし、だからこそ三日には「三日だけの役割」が与えられてきました。祝祭と日常の境目に置かれた、静かな節目の日――それが正月三日です。 三日を代表する風習として、まず挙げられるのが「三日とろろ」です。あまり知られていないかもしれませんが、正月三日の朝に、とろろ芋を食べる習わしで、主に関東から東日本にかけて伝えられてきまし・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
正月二日
正月二日は、元日の張りつめた空気が少し緩み、しかし日常にはまだ戻らない、この独特の時間帯に、日本にはいくつもの「始め」の行事が用意されています。初荷、書初め、姫始め。いずれも年の最初に行う所作ですが、商い、言葉、生命と、社会の表から奥深い私的領域までを静かに広げています。正月二日は、祝祭の余韻の中で「動き出す準備」を整える日なのです。 まず「初荷」です。江戸時代の町では、年明け最初に商品を運び出す・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
今年はどんな年?
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 2026年はどんな年になるのか、西洋占星術と日本の占いが示す「同じ未来、異なる語り方」を調べてみました。未来を語るとき、人は数字や年号に特別な意味を与えます。2026年という年もまた、占いの世界では静かに、しかし確かな重みをもって語られてきました。興味深いのは、西洋占星術と日本の占いが、まったく異なる言語と体系を使いながら、よく似・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
大晦日
大晦日(おおつごもり)は、日本の時間感覚がもっとも濃縮される一日です。現代では「おおみそか」と読むのが一般的ですが、古くは「大晦」「大つごもり」と書き、月が隠れきる夜、つまり一年最後の闇を意味していました。この日は単なる年末ではなく、時間がいったん解体され、再編成される「境界の一日」として意識されてきました。 「晦日」とは月が見えなくなる日を指します。太陰太陽暦のもとでは、月の消失は不安と再生の象・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
師走晦日
師走三十日(しわすみそか)は、暦の上ではただの年末の一日ですが、生活感覚の上ではきわめて重要な日です。翌日の大晦日ほどの華やかさはなく、元日の祝い気分にはもちろん届きません。しかし、だからこそこの日は「年の重み」がもっとも濃く漂う一日でもあります。言ってみれば、一年がまだ完全には終わっていない状態で、しかしもう後戻りはできない、そんな宙づりのような気分の時間です。「あと1日しかない」という焦りの気・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
世界の降誕祭
日本のクリスマスといえば、チキンと苺のケーキを思い浮かべる方が多いでしょう。宗教的な行事というより、年末の華やかなイベントとして定着したこの風景は、世界的に見るとかなり独特です。本来クリスマスは、イエス・キリストの誕生を祝う「降誕祭」であり、その祝い方は国や地域の歴史、宗教観、生活文化によって大きく異なります。 アメリカではローストターキーが象徴的な料理です。感謝祭と同様、大きな七面鳥を囲み、家族・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
冬至
冬至という言葉には、季節の歯車がゆっくりと転換する音が潜んでいます。一年で最も昼が短く、夜が長い日。太陽の力が一年でいちばん弱まる瞬間と言われるこの節気は、なぜか同時に「復活」の気配もまとっています。光が極点までしぼんだその先に、かすかな再生の兆しが芽をのぞかせる──冬至は、暦のなかでもとりわけ象徴性の強い日です。 冬至の本質を捉えるには、まず天文学の視点が役立ちます。地球の公転軌道における太陽高・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
霜月入り
霜月という語を口にすると、たちまち空気が澄んでいくような気がします。和暦の十一月にあたる霜月は、名のとおり霜が日常の風景へと滑り込み、季節の移り変わりを静かに告げる時期です。暦は単なる日付の並びではなく、人々が自然の息づかいを読み取るための“感性の計器”でした。そのため、霜月には冬の気配をとらえる細やかな観察が折り重なっています。「霜月」という呼称自体が、夜明け前の冷え込みを想像させます。地面や屋・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
大雪(たいせつ)
大雪(たいせつ)は、二十四節気のうちで冬の深まりを告げる節目です。「雪いよいよ降り重なる」という意味をもつ語がそのまま名になっています。立冬から約ひと月、季節は静かに歩みを進め、ここで一段階、冬が芯に入るような変化が訪れます。大地は冷気をたっぷりと含み、空は雪を抱く重さを帯び、光さえ淡くなる。この「季節の質感の変換点」の手触りこそ、大雪の魅力です。 寒さが厳しさを増すころ、山間部では本格的な降雪が・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
小雪
晩秋の気配がいよいよ深まり、冬の入り口に立つころ、二十四節気のひとつ「小雪(しょうせつ)」がやってきます。小雪とは文字通り、雪がちらほらと降り始めるという意味で、まだ本格的な冬ではないものの、寒さの中に確かな白の気配を感じさせる節目です。 七十二候では「小雪」は次の三つに分けられます。 初候は「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」。秋までの雨上がりの空にかかっていた虹は姿を消し、空気は澄みながらも冷た・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
立冬
本日から二十四節気の立冬に入ります。立冬と聞くと冬の到来の時期ですが、実際、このところの寒さはそれを実感します。立冬は二十四節気の十九番目にあたり、太陽が黄経二百二十五度に達したときにあたります。朝晩の冷え込みがぐっと強まり、木々の葉が散りはじめ、空気がいっそう澄んでくる頃です。目に見える雪こそまだですが、風の冷たさや陽の短さが、確かに季節の境を感じさせてくれます。立冬は、「冬が立つ」、すなわち冬・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
十三夜
今夜は十三夜です。秋も深まり、空気が澄んでくると、夜空の月がいっそう美しく見えるようになります。旧暦九月十三日の夜にあたる「十三夜(じゅうさんや)」は、十五夜の満月から少し欠けた月を愛でる、日本独自の月見行事です。十五夜の月を「中秋の名月」と呼ぶのに対し、十三夜は「後(のち)の月」あるいは「栗名月」「豆名月」ともいわれ、秋の実りを感謝する夜として古くから親しまれてきました。十五夜が中国伝来の行事で・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
霜降
霜降(そうこう)は、二十四節気の第十八にあたり、秋の終わりを告げる節目です。現在の暦ではおよそ十月二十三日ごろにあたり、太陽が黄経二百四十度の位置に達する日を指します。文字どおり「霜が降りる」時節であり、朝晩の冷え込みがぐっと厳しくなり、草木や屋根の上に白い霜が降り始めるころです。秋の静かな終章であり、冬の前奏曲ともいえるこの時期には、自然のうつろいがいっそう繊細に感じられます。 「霜」は、空気中・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
旧暦9月2日(仏滅甲子)
旧暦や六曜、干支が交わる「9月2日・仏滅・甲子(きのえね)」という日は、暦の上で興味深い重なりを見せる日です。ここでは、その由来や意味、そしてそこから見えてくる日本人の時間感覚について考えてみましょう。もともと「仏滅」は、六曜の一つで「万事に凶」とされる日です。婚礼を避け、葬儀を選ぶ日という俗信が根づいています。しかし六曜そのものは、古代中国の「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」から成・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
紅葉月朔日
旧暦では本日から、9月になります。9月は長月として知られていますが、他にも菊月、紅葉月など風流な異名があります。季節はすでに秋の深まりを見せ、空気が澄み、夜長を実感するころ。虫の音が弱まり、稲刈りが終わって田の畔にはすすきが揺れ、野山は少しずつ赤や黄色に染まりはじめます。今年のように夏が長いと、今の時期から秋が深まるという実感があります。たまには旧暦の世界観を楽しんでみると、「十月なのに暑い」とい・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
秋土用の入り
本日は秋土用(あきどよう)の入りです。暦の上で「季節の変わり目」を告げる静かな節目です。一般に「土用」と聞くと、真夏の「土用の丑の日」を思い浮かべる人が多いですが、実は土用は年に四回あります。立春・立夏・立秋・立冬の直前、つまり次の季節へ移る前の約18日間を指し、それぞれ「春土用」「夏土用」「秋土用」「冬土用」と呼ばれます。秋土用の入りは、立冬の18日前にあたる日です。この時期は、暦の上では秋の終・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節