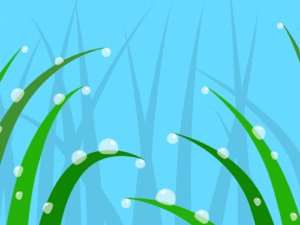その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
手話の雑学9
手話の言語習得についていえば、生後から手話環境にある人は希少です。ほとんどは生後かなり経ってから手話を習得します。それを母語と言い切ってしまうのは、むずかしいのです。それを是認するためには、手話学習以前は無言語であったという仮定が必要です。 ここでよく話題になるのが「狼に育てられた子」の話です。これが「無言語」といえるのかどうかについては議論があります。この件を話すと長くなるので、省略しますが、手・・・
手話の雑学8
手話という言語を社会的にどうとらえるか、について、単純に手話を「ろう文化」「ろう社会」と結びつけて不可分な1体という思想があります。キリスト教の三位一体のような捉え方はただしくないことがわかります。しかし、この「聾の三位一体説」は意外に欧米に浸透しており、日本は今でも信じている人が多いのが現状です。 この思想の問題点は、言語と文化と社会(コミュニティ)を一体化させて、1つの民族のように考えようとい・・・
手話の雑学7
ヨーロッパの手話の始まりはフランスの聾教育からであることが知られています。18世紀半ば、ド・レペという神父が手話による聾教育を始めたとされています。ド・レペ神父は聾児たちにフランス語を教えようとして、その手段として手話を用いたわけです。日本では少し誤解が広がっていますが、ド・レペ神父はフランス語を教えるために手話を用いたわけです。日本でいう「日本語対応手話」という表現を借用すれば、「フランス語対応・・・
白露(はくろ)
二十四節気の一つである「白露(はくろ)」は、今年は9月7日です。朝夕の空気がぐっと冷え込み、草花の上に白い露が宿るようになるとされていますが、今年は猛暑の影響で事情が違うようです。暦の上では秋の深まりを告げる節気であり、夏から秋への季節の移ろいを感じさせる大切な節目です。 二十四節気は農耕や生活の目安として長く受け継がれてきました。その一つひとつをさらに細かく分けたのが「七十二候(しちじゅうにこ・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
手話の雑学6
アメリカは多様化こそが文化であり、それが政治的分断の原因の1つであることも知られています。他にも、中国の政府は必至に統一を図ろうとしていますが、現実には民族が多様化し、それに伴い言語も多様化しています。言語は「普通話」という北京語を全国に浸透させようとしていますが、実際にはまだ方言が色濃く残っています。宗教は建前上禁止という形で統一を図ってはいても、実際には多様な宗教が残ったままです。料理は日本で・・・
手話の雑学5
身振りは文化と深い関係があることはわかりましたが、ここで文化と言語と民族や宗教との関係を改めて考えてみます。 先に、言語と文化と民族や人種、そして宗教には関連があることを説明しましたが、すべてが一致しているケースはほとんどありません。あるとしたら、ごく一部の少数民族だけです。日本では、「日本は単一民族、単一国家」と主張する人が多いのですが、単一宗教だと唱える人は稀有でしょう。宗教については、むしろ・・・
手話の雑学4
あらためて、日本の手話と身振りを比較してみると、たとえば「自分」を表すために鼻を指差すのは日本独特の文化であり、外国では胸を指差す身振りなので、外国の身振りや手話では、鼻を指差すと「鼻」の意味にしかなりません。日本の手話学ではあまり知られていませんが、「手話には文化的な違いがあるという典型的な例」として、欧米の手話学では知られています。 また、手話の最初の方で習う<男>と<女>は日本では身振りと共・・・
手話の雑学3
よく「手話は世界共通ですか?」という質問を受けます。この背景には「身振りは世界共通」という誤解があるように思われます。私たちは外国人とのコミュニケーションで、ことばによるコミュニケーションがむずかしい、と思うと、いわゆる「身振り、手振り」で伝えようとします。なぜ身振りなどが伝わりやすいと考えるのか不思議ですが、「自然に」そう思ってしまうのです。実際、かなりの程度、意図が伝わります。喜怒哀楽などの表・・・
手話の雑学2
手話の指導法は、先生や地域によって、多少の違いはありますが、全国のどこでも、似たような形式になっています。しかし実用的な側面を考えると、「あなたの名前は何ですか?」という日本語は変です。普通の状況では「お名前を伺っていいですか?」とか「お名前は?」といいます。つまり「あなたの名前は何ですか?」という日本語文は手話表現に合わせた文です。こういう「教科書文」はどの言語教育でも普通に存在します。たとえば・・・
手話の雑学1
9月1日から、欧米やその影響下にある国々では学年や企業の年度が始まります。その理由は農耕社会の季節労働に対応するためだと言われています。夏(6〜8月)は農繁期で、子どもたちが収穫や農作業を手伝うために休暇が必要だったからです。夏の終わりで、収穫が落ち着く頃に教育を再開するのが自然でした。ある意味、欧米でも昔は児童労働が当たり前だったのです。秋は気候や農作業が安定する季節で、勉学に適したタイミングと・・・