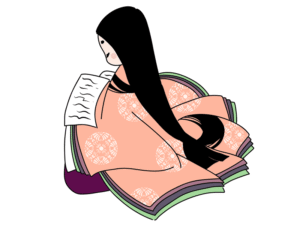漏刻

漏刻(ろうこく)といってもピンとくる人は少ないのですが、天智天皇10年(671)4月25日(旧暦)に漏刻と鐘鼓による時報を開始したとされていることから、そしてそれが現代の暦に換算すると現 在の 6月10日であることから、現在はこの日が「時の記念日」となっています。
日本最古の時計である漏刻 (ろうこく)が大津市に ある近江神宮時計博物館で紹介されています。漏刻というのは水時計であり、大宝律令によって,中務省陰陽寮 (おんみょうりょう)に 属する漏刻博士が守辰丁 (ときもり)を指揮し, 漏刻の 目盛 を見て時刻を知らせることを司っ たとされています。室町時代に外国から機械時計が入って くるまで, この漏刻が時刻制度の基準と定められていたそうです。その構造は,満水池,夜天池, 日天池、平水池と呼ばれる箱が順に階段状に置かれ, その下に刻分壺があっ て、矢が浮かべてあるそうです。まず、満水池に水を満たすと、水は次々と下に移り、刻分壺に入ります。 その壺の水が満たされるにつれて矢は浮き上がります。矢には刻みがつけてあり時刻を知ることができる、という仕組みです。文字だけではわかりにくいかもしれませんが、イラストを見ればすぐに原理がわかる単純なものです。水の落ちる速さを一定に 保つために箱の数を増やしていくのですが、この漏刻は当時の最高水準の技術で 製作されています。(https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/44/1/44_KJ00003518878/_pdf/-char/ja参照)
漏刻は日本の発明ではなく、中国では、実用かどうかは別として、紀元前から漏刻がありました。そして、より正確な水時計をつくるために、様々な工夫、改良が行なわれました。中国における水時計の変遷ついては、山田慶児「古代の水時計」によると、実物として残っている前漢の例は、底に近い側面に出水管のついた銅製の壺で、壺の水が滅ることによって、時間の目盛を刻んだ箭が下がる、という仕組みでした。しかし、これでは、水位が下がると水圧も滅るために出水量が滅少し、時計として遅れることになります。そこで、前漢末頃になると、箭を水を出す壺(漏壺)から別の壺に移し、上下の位置関係に置くように進化しました。上の漏壺から出た水を下の箭がはいった壺(箭壺)が受け、箭が上がるようになるわけです。
水時計の進化の中で、この沈箭漏から浮箭漏への変化は、その第一段階でした。水時計には、漏壺と刻箭という2つの要素のあることが明らかになり、漏壺の漏と刻箭の刻をとって、漏刻というようになりました。漏壺の水位が下がれば箭壺へ流入する水量が滅ります。そこで、上の壺に水が流出した分だけ補充してやれば、水位を一定に保つことができるので、その上にもう一つ壺を置くというように、その後の漏刻の進化は、漏壺を増やしていく方向に進んでいきます。やがて、それぞれの水槽は、サイフォン管によってつながれるようになり、水は一番上の夜天池からサイフォン管を通り、日天池、平壺、萬分壺を経て水海に流入する仕組みに変わります。サイフォン管を用いれば、水面高が不安定になるのを防ぐばかりでなく、水の流量も少なくてすむので、長い時間を計ることができるようになります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |