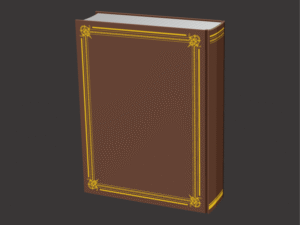暑さと知恵の交差点─夏土用と丑の日

真夏の盛り、食欲も落ち、体力も消耗しがちな時期に話題となるのが「土用の丑の日」です。スーパーや飲食店の店先にはうなぎの幟(のぼり)が立ち、人々はこぞって蒲焼きを求めます。この風習は単なる習慣ではなく、古来の暦と生活の知恵、そして江戸時代の発明家・平賀源内のアイディアが複雑に絡み合った文化です。今年は土用丑の日が19日と31日の2回あります。
土用とは、五行思想に基づいた暦の区分で、春夏秋冬のそれぞれの季節の終わりに挿入される約18日間を指します。「土」は木火金水の五行のうちの一つで、季節の移り変わりを司ると考えられました。そのため、春の終わりには「春土用」、夏の終わりには「夏土用」のように各季節ごとに土用と呼ばれる期間が設けられています。夏土用は、一年でも最も暑さが厳しい時期であり、体調を崩しやすい「気の変わり目」とされています。この期間中には「間日(まび)」と呼ばれる特別な日もあり、土をいじることが避けられたり、農作業や建築作業に配慮が必要とされてきました。土用の期間中で「丑の日」にあたる日が「土用の丑の日」と呼ばれます。干支は12日周期で回るため、土用の間に丑の日が1回、または2回入ることもあります。夏の土用の丑の日は、現代日本では「鰻の日」となっていますが、それは昔、丑の日には「う」のつく食べ物を食べると夏バテ予防になるという民間信仰がありました。梅干し、うどん、瓜、そして「ウナギ」もその一つだったのです。鰻ば、本来、夏の暑い日には食欲がわかないはずの脂の乗った食材です。では、なぜわざわざこの季節に食べるのでしょうか。その答えの鍵を握るのが、江戸時代の奇才・平賀源内です。源内は本草学者、蘭学者、発明家として知られていますが、その中でも現代的マーケティングの先駆けともいえる逸話があります。ある鰻屋が夏場に売り上げが落ちることを源内に相談したところ、源内は「土用の丑の日」という看板を店先に掲げるよう助言しました。「丑の日にはうなぎを食べると体に良い」という言い伝えを利用し、見事に客足を取り戻すことに成功したのです。これが、今日の「土用の丑の日=うなぎ」の風習の始まりとされるエピソードです。
この話がどこまで史実かは諸説ありますが、源内の創意工夫と発信力の高さを象徴する話であり、日本人の暦と食文化の融合を象徴する出来事でもあります。鰻にはビタミンAやB群、D、Eなどの脂溶性ビタミンが豊富に含まれ、たんぱく質やカルシウム、鉄分も多く含まれます。脂肪分が豊富でありながら消化もよく、滋養強壮の効果が高いとされ、夏バテに効果があると信じられてきました。また、江戸時代にはうなぎが庶民の手の届く食材であり、蒲焼きにする文化もすでに根づいていたため、丑の日のうなぎという組み合わせが定着しやすかったのでしょう。
現代でも「土用の丑の日」が近づくと、食品業界やメディアは一斉に鰻を取り上げます。ただし、近年はうなぎ資源の枯渇が深刻化しており、養殖に頼る状況が続いています。価格の高騰や環境保護の観点からも、うなぎを年中大量に消費することへの問題意識も高まりつつあります。
最近では代替として「う」のつく他の食材を提案する動きも見られます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |